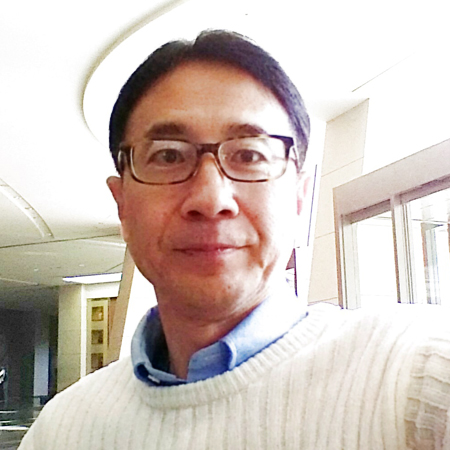… … …(記事全文9,345文字)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
山田順の「週刊:未来地図」
No.729 2024/07/04
バイデン老化パニック(3)
老化の正体とは? 病気なら治療で治せるのか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大統領候補ディベートで、失態を演じてしまったバイデン大統領。敵はトランプ前大統領ではなく、「老化」(エイジング)であることがはっきりしてしまった。
やはり、老化には誰も勝てないのか?
調べてみると、最近は「老化は防げる病気」とされるようになり、人類の夢「不老」を実現すべく、アンチエイジング(抗老、不老)、長寿の研究が加速している。その研究をリードしているのは、もちろんアメリカで、研究への巨額投資が集まっている。
[目次] ─────────────────────
■アンチエイジング研究に巨額投資
■ジェフ・ベゾスは不老研究に30億ドル
■長寿スタートアップ向けのファンドも誕生
■日本におけるアンチエイジング研究
■FDAは現時点で「老化は自然現象」
■FDAが抗認知症新薬「ドナネマブ」を承認
■すでに人類は「不老長寿」を手にしている
■アンチエイジング研究の4大アプローチ
■なぜ、ヒトは老化するのか? 原因は?
■老化は自然現象ではなく「治療できる病気」
■サーチュイン遺伝子の働きを制御する「NAD⁺」
■「老化細胞」と「セノリティクス」の開発
■世界には「老化しない」長寿動物がいる
■遺伝子よりも生活習慣のほうが大きく影響
■「NYタイムズ」の「不老不死の魔法の薬」記事
■人気急落で撤退要請。ジョンソン大統領の例も!
─────────────────────────
■アンチエイジング研究に巨額投資
残念ながら、バイデンは早く老いすぎたと言える。もう少しすれば、人類の寿命は120歳まで伸びる可能性があったからだ。現在、過去のどんなときより、人類は「不老不死」を求め、「アンチエイジング」の研究が加速化している。
デジタルエコノミーの時代がやって来て、GAFAMなどのビッグテックに富が集中しているが、そのリーダーたちはみな、アンチエイジングの実現に惜しみなく巨額資金を投じている。
たとえば、グーグルの共同創業者のラリー・ペイジは、2013年に、アンチエイジング研究を行うベンチャー「キャリコ」(Calico)を設立。長寿を研究開発の目標として、加齢や寿命をコントロールする因子の研究のために、しており15億ドルを投じている。
■ジェフ・ベゾスは不老研究に30億ドル
アマゾンのジェフ・ベゾスとペイパルのピーター・ティールは、2016年、「老化細胞除去薬」(セノリティクス:senolytics)の開発を目指すバイオ企業「ユニティ・バイオテクノロジー」(Unity Biotechnology)に巨額投資をした。
さらに、ジェフ・ベゾスは、2021年に起ち上げられ、日本の山中伸弥教授もアドバイザーとして参画しているベンチャー「アルトス・ラボ」(Altos Labs)に出資した。その出資金が30億ドル(約4800億円)と巨額だったため、「アルトス・ラボ」には大きな注目が集まった。
マサチューセッツ工科大学(MIT)が発行する科学技術誌「MITテクノロジーレビュー」によると、「アルトス・ラボ」は、細胞を再プログラムする技術の開発を目指し、将来性のある科学者を年俸100万ドルで採用しているという。
■長寿スタートアップ向けのファンドも誕生
ChatGPTをつくったハイテク企業「オープンAI」のCEOサム・アルトマンも、アンチエイジング研究のスタートアップに巨額投資したことで話題になった。投資先は、「レトロ・バイオサイエンス」(Retro Biosciences)で、投資額は1億8000万ドル(約288億円)。
レトロ・バイオサイエンスは、「ヒトの寿命をあと10年伸ばす」ことをミッションとして設立された企業で、アメリカではこうしたスタートアップを「ロンジェビティ・スタートアップ」(longevity startups)と呼んでいる。ロンジェビティ(longevity)とは長寿のことだ。
ここ数年で、アメリカにはロンジェビティ・スタートアップが続々誕生し、そこに世界中の資金が集まっている。長寿研究のスタートアップに特化して投資する「ロンジェビティ・ファンド」(Longevity Fund:長寿ファンド)も誕生している。その一つに、サウジアラビア王室が10億ドル(約1600億円)で立ち上げた「ヘボリューション財団」(Hevolution Foundation)がある。
長寿研究のスタートアップ向けに「アメリカの高齢者の認知や筋肉などを10年若返らせたら賞金1億ドル」というコンテストの開催も発表されている。