佐々木俊尚の未来地図レポート
佐々木俊尚(作家・ジャーナリスト)

佐々木俊尚(作家・ジャーナリスト)

世界はこれからどうなっていくのか?
テクノロジーは社会をどう進化させていくのか?
人と人の関係はどう変化していくのか?
この不透明な時代の先に何が待ち受けているのかを、
独自の鋭い視点から切り出し、未来を見通します。
毎号きわめて濃密な特集記事に加え、ブックレビュー/ライフハック/特選キュレーション
など盛りだくさんのメニューをご提供。さらには本メルマガ限定で日本では紹介されていない英語圏の記事をまとめて紹介しています。
配信日は毎週月曜日午後5時。激動の一週間をスタートさせるのにふさわしい知的刺激をどうぞ。


価格:550円/月(税込)

価格:10,000円/月(税込)

価格:990円/月(税込)

価格:660円/月(税込)

価格:550円/月(税込)

価格:2,200円/月(税込)

価格:660円/月(税込)

価格:550円/月(税込)

価格:550円/月(税込)

価格:550円/月(税込)

価格:1,000円/月(税込)

価格:0円/月(税込)

価格:1,100円/月(税込)

価格:880円/月(税込)

価格:660円/月(税込)

価格:880円/月(税込)

価格:1,100円/月(税込)

価格:3,850円/月(税込)

価格:13,200円/月(税込)

価格:9,900円/月(税込)

価格:1,056円/月(税込)

価格:550円/月(税込)

価格:1,300円/月(税込)

価格:880円/月(税込)

価格:330円/月(税込)

価格:5,500円/月(税込)

価格:217,800円/月(税込)

価格:880円/月(税込)
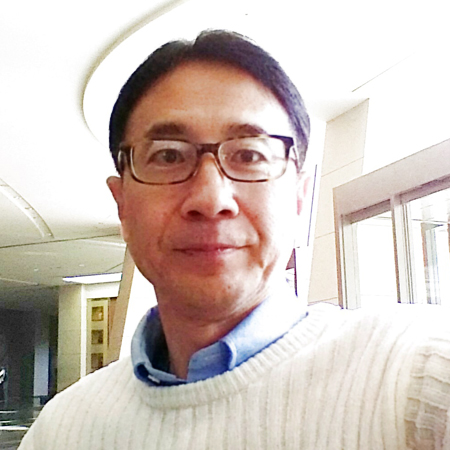
価格:1,100円/月(税込)

価格:1,100円/月(税込)

価格:880円/月(税込)

価格:1,100円/月(税込)

価格:1,018円/月(税込)

価格:3,036円/月(税込)

価格:4,400円/月(税込)

価格:500円/月(税込)

価格:2,200円/月(税込)

価格:2,200円/月(税込)

価格:30,555円/月(税込)

価格:9,900円/月(税込)

価格:880円/月(税込)

価格:2,200円/月(税込)

価格:7,914円/月(税込)

価格:855円/月(税込)

価格:1,500円/月(税込)

価格:6,620円/月(税込)

価格:1,980円/月(税込)

価格:660円/月(税込)

価格:8,860円/月(税込) 、2026年01月から9,900円/月(税込)に変更します。

価格:9,045円/月(税込)
月途中からサービス利用を開始された場合も、その月に配信されたウェブマガジンのすべての記事を読むことができます。2025年12月19日に利用を開始した場合、2025年12月1日~19日に配信されたウェブマガジンが届きます。
利用開始月を選択することができます。「今月」を選択した場合、月の途中でもすぐに利用を開始することができます。「来月」を選択した場合、2026年1月1日から利用を開始することができます。
クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、d払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払いをご利用いただけます。
クレジットカードでの購読の場合、次のカードブランドが利用できます。




キャリア決済での購読の場合、次のサービスが利用できます。



銀行振込での購読の場合、振込先(弊社口座)は以下の銀行になります。


クレジットカード決済によるご利用の場合、解約申請をされるまで、継続してサービスをご利用いただくことができます。ご利用は月単位となり、解約申請をした月の末日にて解約となります。解約申請は、マイページからお申し込みください。
銀行振込、コンビニ決済等の前払いによるご利用の場合、お申し込みいただいた利用期間の最終日をもって解約となります。利用期間を延長することにより、継続してサービスを利用することができます。
