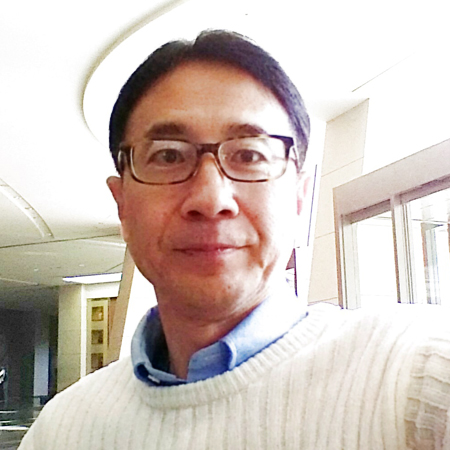… … …(記事全文7,045文字)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
山田順の「週刊:未来地図」
No.725 2024/06/18
(配信:2024/06/27)
完全に詰み!「永久円安」「永久インフレ」で、
徐々に破綻に向かう日本経済
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(このメルマガは、本来なら6月18日に配信する予定でした。それが、私の手違いで1週遅れになってしまいました。申し訳ありません。1週遅れですが、内容はタイムリーです。とうとうドル円は160円を突破し、今日は160.58円で引けています)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
円安とインフレが続いている。もはや「永久円安」「永久インフレ」状態だ。賃金が上がらないから、この状況はスタグフレーションで、景気はどんどん悪化する。
しかし、この状況から、日本経済が脱出する手立てはない。先週、日銀の政策決定会合ではっきりしたのは「なにもできない」ということだった。財務省も為替介入はしたが、焼け石に水。政府はあろうことか増税をやめず、まだ国債によるバラまきを続けるつもりでいる。
これでは、日本経済は徐々に衰退し、国民生活は坂道を転げ落ちるように貧しくなっていく。
[目次] ─────────────────────
■「動かない」ではなく「動けぬ」日銀
■なにもできない日銀、完全に詰んだ金融政策
■円安の本当の原因は国債の大量発行
■金利を上げられない世界一の「債務大国」
■投機筋と言っても合理的な市場プレーヤー
■投機筋に「どうぞ」と日銀が“お墨付き”
■絶妙のタイミングの介入も“焼け石に水”
■介入資金のタマ、ドル預金はいずれ尽きる
■円安インフレによって賃金はどうなったか?
■インフレ進行で得をするのは借金政府だけ
■最終的には心理ゲームでゲーオーバーに
─────────────────────────
■「動かない」ではなく「動けぬ」日銀
さる6月14日、日銀の政策決定会合が開かれた。金融経済のことなどほとんどわからない大多数の国民、国民のことを考えているようで考えていないメディア、そして、曲学阿世の専門家たちは、「円安、物価高をなんとかしろ。金利を上げろ」と騒ぎ立ててきたが、日銀はほぼ動かなかった。
その結果、ドル円は再び160円を目指す展開となり、週明けの6月17日には日経平均が800円も下がった。
日経新聞のウエブは、この状況を見越して、17日早朝に
『「動けぬ日銀」160円試す市場 円安圧力なお、視線は7月』という記事をアップした。記事は、以下のように述べていた。
《金融市場では週明け以降も円安圧力が残るとの見方が広がっている。国内景気の弱さから日銀は追加利上げに踏み切りづらく、日米金利差が開いた状況が続くとの思惑があるためだ。7月末の金融政策決定会合へ向け、1ドル=160円を試す展開となりそうだ。》
記事の見出しに「動けぬ日銀」とあることが、現在の状況を象徴している。「動かない」ではなく「動けない」のだ。
■なにもできない日銀、完全に詰んだ金融政策
今回の政策決定会合について、一部メディアは素直に「国債買い入れを減額する方針を決めた」と報道したが、7月から国債買い入れの減額が始まるわけではない。削減計画が示されるだけで、始まるのは早くて8月だ。
現在、日銀の国債の保有残高(6月10日現在)は、約584兆円。なんと、GDP比でほぼ100%であり、FRBのアメリカ国債(財務省証券)保有額の対GDP比は約20%だから、とんでもない数字である。世界でこんな国は、破綻国家以外にあり得ない。
これを、今回の決定で減らす方向になったわけだが、これは本来の金融引き締めではない。なぜなら、購入額を減らすだけで、金融緩和は依然として続いていくからだ。
日銀の植田和男総裁は、減額の方針を決めたことについて、「金融市場における長期金利の自由な形成を促進していく」と説明した。しかし、金利を市場に任せたら大変なことになるので、できようがない。それで、減額の内容に関しては「相応の規模で」としか言えなかった。
本来、インフレに対処するなら、緩和をやめて金利を上げるべきである。しかし、国債残高が大きすぎてそれができない。もはや、金融政策は詰んでしまって、日銀は身動きが取れないのだ。
■円安の本当の原因は国債の大量発行
こんなことになってしまった原因は、もちろん、長年にわたる放漫財政にある。それをアベノミクスが加速させ、引き返せなくしてしまったのである。
緩和をやめれば金利が上がる。金利が上がれば、国債費が増え、財政は逼迫し、その行き着く先は財政破綻である。
なにしろ、安倍晋三元首相は、「日銀は政府の子会社」と言い放ち、中央銀行の独立性をないがしろにしてしまった。
財政法第5条は、日銀引き受けによる国債発行を禁止している(国債の市中消化の原則)。しかし、安倍・黒田コンビが始めた異次元緩和は、いったん市中を通したとはいえ、日銀が引き受けるのを前提としているので、これは禁じ手の「財政ファイナンス」である。
日銀が国債を直接引き受ければ、金利を気にすることなく、政府はいくらでも国債を発行することができる。まさに「打ち出の小槌」を手に入れたのと同じで、政府は国債を発行しまくり、2012年末からこれまでの11年間で371兆円も積み上げてしまった。
この間、マネタリーベース(マネーストック)は拡大し続け、日米で比較すると、日本はアメリカの約2.5倍もの紙幣を発行した。2012年当時、ドル円は83円だったが、いまや158円(6月17日)。ドルの約2.5倍も発行される円が安くなるのは当然の成り行きである。