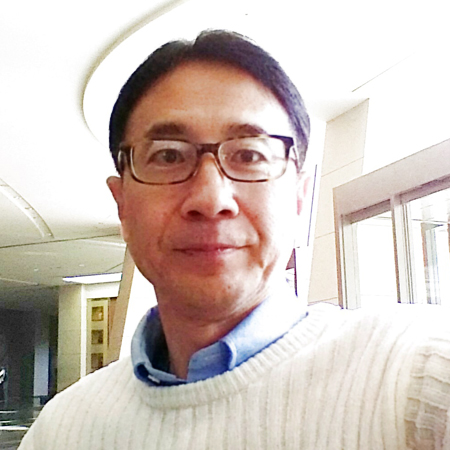■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ <1ヶ月にビジネス書5冊を超える知識価値をe-Mailで> ビジネス知識源プレミアム(週刊:648円/月):Vol.994 <994号:負債が主導してきた世界経済の向かうところ(1)> 2019年3月6日:世界の主体別負債とGDP比の上昇 ウェブで読む:https://foomii.com/00023/2019030710000052664 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ホームページと無料版申し込み http://www.cool-knowledge.com 有料版の申込み/購読管理 https://foomii.com/mypage/ 著者へのメール yoshida@cool-knowledge.com 著者:Systems Research Ltd. Consultant吉田繁治 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ おはようございます。2010年代の世界経済を主導していたのは、中国のGDP成長と、米国の経常収支の赤字です。 GDPは商品の生産額であり、経常収支は、「貿易収支+海外工場への直接投資と債券投資がもたらす所得収支」です。 中国のGDPの成長(商品生産額の増加)と、米国の経常収支の赤字は、日本にとっては、「外需」です。 2010年代のわが国では、外需について、過去の古典的な通念を変更する必要があります。まず、これを書きます。 【日本にとっての外需の構造】 日本では、内需(世帯消費+住宅建設+企業の設備投資+政府消費+公共投資)の成長は、ほとんど0%でした。 外需である輸出と、経常収支の黒字の、円換算での増加(つまり円安)が、GDPを成長させる要素になっていたのです 端的に言えば、アベノミクスは、円安による外需頼りの成長でした。経常収支のうち貿易収支の黒字は、2007年は14兆円でしたが、2018年は、1.2兆円に減っています。 【為替差益を増やす円安】 円安になると、日本の株価が上がる傾向が強いのは、企業の所得(EPS:1株当たり利益)になる経常収支が、ドルでは同じ金額でも、円安の円換算では、増えるように見えるからです。… … …(記事全文12,839文字)