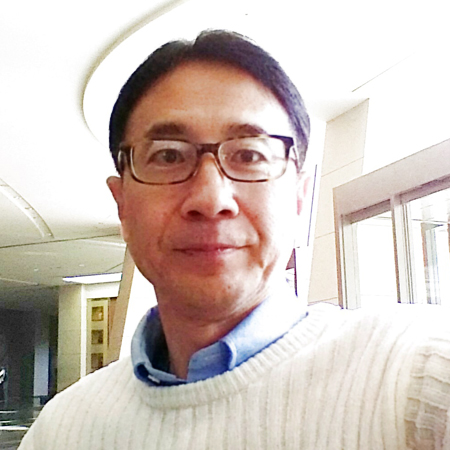… … …(記事全文2,358文字)現在の日本は、所得(給与)の伸びが物価の上昇に追いつかず、実質賃金が下落を続けている。特に、昨今は「きまって支給する給与」の実質値が対前年比を上回ることが、全くなくなってしまった。
【日本の実質賃金指数(きまって支給する給与、対前年比%)の推移】
http://mtdata.jp/20250321-1.jpg
実質賃金が下落し続けていることを受け、石破内閣は、
「生産性を引き上げ、実質賃金を引き上げるべき」
と、「民間企業」に責任を押し付けてくるわけだが、無茶な話だ。
内部要因として、実質賃金は生産性と労働分配率で決まる。企業が生産性向上の投資を行い、労働分配率を高めれば、確かに実質賃金は上がる。とはいえ、企業が投資や労働分配率引き上げをするか否かは、あくまでその企業の経営判断である。政府に言われたから「やる」という話にはならない。日本は社会主義国家ではない。
実質賃金には、外部要因として輸入物価と消費税が影響を与える。輸入物価が上昇すれば、よほど生産性や労働分配率が上がっていない限り、実質賃金は下がる。
もっとも、昨今の輸入物価は円ベースで見ても「高止まり」が続いている。つまりは、上がっていない。
それ以前の話として、日本政府が輸入物価に影響を与えることは難しい。
というわけで、二つ目の実質賃金に影響を与える外部要因が、消費税。
政府が消費税を引き下げれば、物価が下落するため、実質賃金は上昇する。もっとも、日本政府は(今のところ)実質賃金を確実に引き下げる消費税減税については、議論しようとらしていない。
となれば、賃金水準の動向に注目しなければならないわけだが、実は「政府が支払う公務員給与」と「民間企業の給与」は、GDPにおける取り扱いが異なるのだ。
なぜなのだろうか。