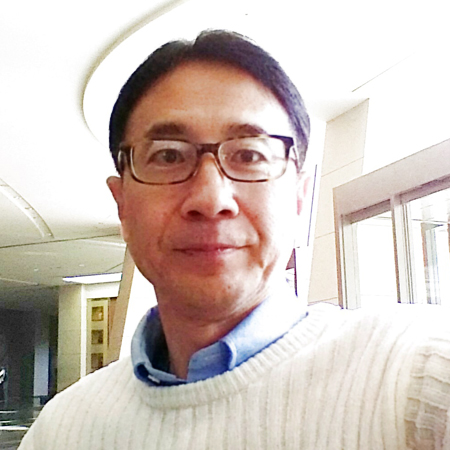━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 山田順のメールマガジン「週刊:未来地図」 No.578 2021/11/16 やがて世界経済の成長は止まる! 早まる人口減で2050年から投資環境は激変 ウェブで読む:https://foomii.com/00065/2021111609000087441 EPUBダウンロード:https://foomii.com/00065-87622.epub ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回は、近未来の話をしてみたい。「COP26」も大きな成果もなく終わり、日本は日本で岸田内閣がわけのわからない「新しい資本主義」を始めた。中国経済は、不動産が不良債権の山に突き当たり失速している。 そんななかで、世界を見渡してみると、このところずっと上がり続けているNY株価だけが、突出して明るい話題となっている。しかし、これがいつまで続くだろうか? 今後も何度かバブル崩壊は起こるだろうが、世界経済はは成長し続ける。株価も上下動を繰り返しながらも上がっていくというのが、現在の「世界観」である。しかし、それも2050年まで。それ以後は、世界的な人口減で、世界経済は歴史上初めて失速する。 [目次] ────────────────────────────── ■バブル崩壊は? 株価は永遠に上がり続けるのか? ■アクティブかパッシブかが無意味になる ■ネットとAI時代、誰もほかの誰かを出し抜けない ■人口爆発は終わり、やがて減少が始まる ■「プラスサム」から「マイナスサム」に ■世界全体の合計特殊出生率は下がっている ■各国の人口は今後どうなっていくのか? ■2050年、世界の6人に1人が高齢者になる ■生産年齢人口の減少による経済衰退 ■移民受け入れもやがて限界が来る ■少子高齢化先進国、日本の未来はどうなる? ────────────────────────────────── ■バブル崩壊は? 株価は永遠に上がり続けるのか? 11月に入ってNY株価は3万6000ドル台に乗せて史上最高値を付けた後、好調に推移している。それに比べると、日本株は3万円台に1度は乗せたものの、その後は低迷したままだ。 これは、日米の国力の違い、金融政策の違いから言って当然のこと。「NY株はバブルだ」という声も根強いが、実体経済から言ってバブルなのは、明らかに日本のほうである。 ただし、NY株も、コロナによる金融バブルなのは明らか。いずれ弾けるだろうが、それがいつかは誰にもわからないし、また、弾けたとしても、その後、また上がるだろう。なぜなら、アメリカ経済は今後も成長を続けるからだ。成長を続ける限り、株価は下がったとしても長期的には上がっていく。 そこで、思い出すのは、「投資の神様」とされるウォーレン・バフェットの投資の基本方針だ。バフェットはこう言ってはばからない。 「Our favorite holding period is forever.」(われわれが好む株式保有期間は永遠である) 長期保有、それも“永遠”が投資だと、バフェットは言っているのだ。バフェットは、この考えをさらに強めて、こう言ったことがある。 「NYダウは今後100年で100万ドルになる」 しかし、こんなことは絶対にありえない事態が、いま静かに進行している。世界の経済成長は間もなく止まるのだ。 ■「パッシブ運用かアクティブ運用か?」 投資の世界では、「パッシブ運用かアクティブ運用か?」ということが常に言われている。これは永遠のテーマと言っていい。 パッシブ運用とは、株やファンドに投資する場合、あらかじめ設定されたベンチマークに対して、それと同程度の成果を目指したポートフォリオを構築して運用する方法。 ベンチマークには、たとえば「S&P500」といった株価インデックスが用いられるため、「インデックス運用」とも言われる。要するに、銘柄などを選ばずに市場全体に投資する方法だ。 これに対してアクティブ運用は、あらかじめ設定されたベンチマークに対して、それを上回る成果を目指したポートフォリオを構築して運用する。つまり、株式投資なら銘柄(「ブルーチップ」と呼ばれる優良株)を選ぶ。 そこで、「さあどちらにすれば運用実績が上がるのか」(つまり儲かるのか)と、これまで比較されてきたが、結論としては、パッシブ運用である。現在における投資の世界の常識では、「アクティブ運用はパッシブ運用に勝てない」ということになっている。 短期的な投機は別として、長期で見ると、たとえばNY市場で銘柄を選んで運用するより、「S&P500」に連動するファンドに投資する、日本市場なら「日経平均連動型ETF」に投資するほうがはるかに効率がいいのだ。 ■ネットとAI時代、誰もほかの誰かを出し抜けない なぜ、アクティブ運用はパッシブ運用に勝てないのだろうか? その答は単純である。アクティブ運用で実績を上げるためには、銘柄を選ばなければならない。これに失敗すれば、投資は失敗する。そのため、銘柄選定にあたっては、ほかの運用者がまだ気がついていない投資価値にいち早く気付く必要がある。投資家あるいは投資家からの資金を預かるファンドマネジャーは、豊富な情報と鋭い投資眼を持っていなければならない。 しかし、ネットで情報が自由に流れ、AIが瞬時に判断を下せるこの時代に、誰が人を出し抜く情報を得られ、鋭い判断を下せるだろうか。 「効率的市場仮説」(Efficient Market Hypothesis、EMH)というのがある。これは、すべての利用可能な情報が完全に市場価格に反映されているとする仮説で、いまの市場は、インサイダー取引が成立しない限り、誰に対してもオープンである。誰もほかの誰かを出し抜けない。 投資信託などの統計では、アクティブ運用の投信やファンドの4分の3はパッシブ運用(インデックス)に負けている。日本のアクティブファンドでは、主に日本株に投資をするファンドの約7割がインデックスに勝てず、外国株に投資するファンドはほとんどが勝てていないという結果が出ている。 ところがいずれ、このパッシブ運用が終焉する日が来る。市場全体に投資しても、市場そのものが収縮してしまうのである。 ■人口爆発は終わり、やがて減少が始まる 2021年8月の日本経済新聞に『人類史 迫る初の減少』という記事が掲載された。この記事によると、世界の人口は爆発的な膨張が終わり、初めて下り坂に入ろうとしているという。また、ほかの新聞、経済誌などにも、同じような記事が次々と掲載された。 つまり、人口増とともに続いてきた経済成長はやがて止まるというのだ。 こうした記事の情報源は、ワシントン大学が2021年7月に発表した人口予測レポートである。これまで国連は、世界人口は「2100年に109億人となるまで増え続ける」(中位推計)として人口爆発を警告してきた。ところが、ワシントン大学は、「2064年の97億人をピークに世界人口は減少する」と発表したのである。 *参照グラフ:世界人口の推移グラフ(日経新聞掲載のもの)新型コロナによるパンデミックの報道でかき消された感があるが、このレポートの衝撃は大きかった。 なぜなら、人口増と経済成長はパラレルで、人口が増えることで世界経済は成長を続けてきたからである。ところが、そうした歴史は21世紀の半ばで終わるというのだ。 ■「プラスサム」から「マイナスサム」に 現在、世界の人口研究者の間では、国連の人口が増え続けるという予測は、多く見積もりすぎているという見解が主流だ。ワシントン大学のレポートはそれを明らかにしただけで、それほど驚くことではないという。 人口統計を専門にしている学者に言わせれば、世界人口は2040年から2060年の間に90億人で頂点に達し、その後は減少に転じる可能性が高いという。 仮に2050年から人口減に転じるとすると、その前後には、「シンギュラリティ」 (singularity)もあるし、地球温暖化による「気温上昇1.5度」も控えている。まさに、歴史のターニングポイントだ。 実際、すでに25カ国前後の国で人口は減り始めている。この傾向は今後も続き、人口減少国数は2050年までに35カ国を超えるだろうと言われている。 すでに人口減に転じた国の筆頭は、わが日本である。そして、韓国、スペイン、イタリア、東欧の多くの国々で人口は減り始めている。日本、スペインなど23カ国は、2100年までに人口が半減すると予測されている。 そこで、人口減が経済成長をマイナスにするという点で考えると、投資におけるパッシブ投資が成り立たなくなることがわかる。 これまでの人口増社会においては、投資は「プラスサムゲーム」だった。これは、ゲームに参加しているプレイヤーの損得の合計がプラスになることを言う。つまり、インデックスで市場全体に投資していれば、これまでは儲かったのである。 しかし、ひとたび人口減に転じれば、このゲームは、プラスマイナスがゼロの「ゼロサムゲーム」か、マイナスになる「マイナスサムゲーム」になってしまう。 パッシブ投資で誰もが利益を分かち合えた時代は終わりを告げ、誰かが儲かれば誰かが確実に損をするという時代となって、アクティブ投資に成功した者しか、市場での勝者はいなくなってしまうのだ。 ■世界全体の合計特殊出生率は下がっている 人口減をもたらす最大の原因は、女性が子どもを産まなくなったことである。ワシントン大学のレポートによると、 出生率はこの先どんどん低下し、少子化が加速するという。 少子化の背景には、技術革新などによる経済発展がある。経済発展によって生活が豊かになるにつれて、死亡率は低下し、社会は「多産」から「少産」へと向かう傾向が強まった。まさに、20世紀はそういう世紀だった。 国連の統計資料によれば、5歳未満児の死亡率は国によってバラつきはあるが、1990〜1995年には出生数1000人あたり91人だったが、2015〜2020年は40人にまで低下した。途上国の多くが経済発展したため、全世界の合計特殊出生率(以下、出生率と略す)は、1985〜1990年は3.44だったが、2015〜2020年には2.47へと低下した。 1950年以降の出生率の推移を見ると、ほとんどの国・地域で著しく下落している。2015〜2020年で4.72と世界最高水準の「サブサハラ」(サハラ砂漠以南のアフリカ)は、1950〜1955年は6.51だった。北アフリカ・西アジアは2015〜2020年は2.93だが、1950〜1955年は6.57だった。ちなみに、日本の現在の出生率は、1.36である。 出生率が2.1を下回ると、人口は減少に転じるという。 1950年には、1人の女性が生涯に産む子どもの数は平均4.7人だった。ワシントン大学のレポートでは、世界全体の出生率は2100年までには1.7を下回るとしている。 ■各国の人口は今後どうなっていくのか? それでは、世界の国別に今後、人口がどうなっていくのかを見てみたい。 まずはわが国だが、日本の人口はピーク時の2017年には約1億2800万人だったが、今世紀末までに5300万人以下に減少すると予測されている。まさに、半減してしまうのだ。 イタリアも同じく半減する。現在の約6100万人から約2800万人へと、劇的に減少する。スペインやポルトガル、そのほかの欧州各国も自然増は見込めず、移民を大量に入れなければ人口は減り続ける。イギリスは、いま大量の移民を受け入れているが、それでも2063年に約7500万人となってピークを迎え、2100年には7100万人に減少する見通しだ。 アジアでは、タイ、韓国も同じ道をたどる。 現在の世界で、もっとも人口の多い中国は、ほとんどいまの約14億人がピークで、今後4年以内に減少に転じ、その後は2100年までにほぼ半減して約7億3200万人になるとされている。そのため、今後はインドが人口世界一になるが、インドもまたしばらくして減少に転じる。 このようななかで、21世紀前半のいまもなお人口増を続けているのがアフリカ諸国だが、今後はその増加スピードはどんどん衰えていく。前記したように、サブサハラの出生率は、2015〜2020年の4.72から2045〜2050年には3.17に落ちる。そして、2065〜2070年はさらに下がって2.62となり、2085〜2090年は2.28、2095〜2100年には2.16となる。 つまり、2100年には、サブサハラでさえも人口減に転じるのだ。 ■2050年、世界の6人に1人が高齢者になる 出生率の低下、つまり少子化の進行と並行して起こっているのが、高齢化だ。世界の高齢者人口(65歳以上の人口)は2018年に初めて5歳未満の子どもの数を上回った。この傾向はさらに加速し、2045年には15〜24歳の若者の人数も追い越す。 高齢者人口と高齢化率の推移を見ると、2020年は、全人口の9.3%にあたる7億2760万人が高齢者になった。これは、世界の11人に1人が高齢者ということだ。 しかし、このままのペースでいけば、2050年には高齢者人口は15.9%の15億4885万2000人に達し、世界の6人に1人が高齢者となる。さらに、2080年には20.2%、2100年は22.6%に達する。 当然だが、75歳以上の高齢者も増加傾向をたどる。2020年には2億6928万5000人(総人口の3.5%)から、2100年には13億4762万9000人(12.4%)に膨らむ。 世界規模で高齢化が進むのは、各国の平均寿命が延びていくからだ。1990〜1995年に64.56歳だった世界の平均寿命は、2015〜2020年に72.28歳にまで伸びた。そして、2050〜2055年には77.35歳になると予測されている。 ■生産年齢人口の減少による経済衰退 少子高齢化の進行は、必然的に、生産年齢人口(15歳〜64歳)の減少をもたらす。働く世代が減っていくのだ。そうなれば、生産も消費も減る。経済成長など望むべくもなくなる。 国連の人口予測の中位推計を見ると、世界全体の生産年齢人口は、2020年の50億8354万4000人から、2050年には61億3052万3000人となって約10億5000万人増える。そうして、2090年に65億3630万7000人でピークを迎えるが、その後はじょじょに減っていく。 したがって、全体の人口減少ほど脅威とは言えないが、国別に見ると、影響は大きいと言わざるをえない。 なにしろ、人口大国の中国とインドが劇的に減っていくからだ。つまり、中国とインドの経済成長は、今後、ある時点でストップすることになる。 人口減、とくに生産年齢人口が減ることは、国単位で考えると、国力の低下をもたらす。たとえば、誰が国を支える税金を払うのか、誰が高齢者のための医療費を払うのか、と考えてみればいい。 すでに、日本は生産年齢人口の減少に入っており、それとともに、まったく成長できない国になってしまった。 少子高齢化による生産年齢人口の減少と、人口そのものの減少がなにをもたらすか? なにも将来予測をしなくとも、いまの日本を見れば明らかだろう。 ■人口は増え続け19世紀以降に人口爆発した 人類の歴史を振り返ると、人口は常に増加してきた。19世紀以前は明確なデータが存在しないため、研究者ごとに数値に大きな違いがあるが、おおまかに振り返ると次のような経過をたどって、世界人口は増加してきた。 紀元前8000年ごろ(1万年前)、中東で農耕が始まったとき、人類の人口は500万人ほどだった。これは日本で言えば福岡県とほぼ同じ規模、世界で言えばシンガポール、フィンランドと同じ規模だ。 農耕革命の影響は大きく、以後、人類人口は一気に増えて、西暦1年ごろに3億人に達する。 その後、中世までの増加は漸減的で1650年ごろに5億人となった。食料生産技術や医学、公衆衛生の発達が遅れていた時代は餓死や病死も多く、人口増加のペースは緩やかだったからだ。 それが、18世紀の産業革命以降は、増加ペースが加速する。1804年に10億人、1900年には16億人を突破する。そして、20世紀はまさに人口爆発の世紀となり、1950年代に25億人を突破すると、20世紀末の1987年には50億人、1999年には60億人に達した。 国連では、世界人口が50億人に到達したと推計される1987年7月11日を「世界人口デー」としている。 次が、ここ約200年の人口爆発の年代記である。 1804年 10億人 1927年 20億人 1959年 30億人 1974年 40億人 1987年 50億人 1999年 60億人 2011年 70億人 2021年 78億7500人(国連『世界人口白書2021』) *参照グラフ:世界人口の歴史的推移(「Gigazine」より)
■少子化対策、人口増政策はことごとく失敗 このように、世界人口の推移を振り返れば、これが経済発展とパラレルなのがわかる。科学、技術、医学などが発展し、食糧生産が飛躍的に増えるのと並行して世界人口は増え続けた。これを逆から言えば、人口が増えなければ、経済はスローダウンするということだ。 すでに、少子化に見舞われた国々では、将来の人口減を見越して、あらゆる少子化対策、人口増加政策を導入して、人口が減ることを阻止しようとしてきた。手厚い出産手当、児童手当、育児休業制度、保育サービスの拡充などが少子化対策の柱だが、これまでに画期的な成功例はない。 欧州では、フランス、スウェーデンが出生率引き上げの成功例とされるが、それでも1.90までが精一杯で人口維持に必要とされる2.1に達していない。 シンガポールは、アジアの国のなかで世界に先駆けて少子化対策に取り組んだが、世界最低水準の1.14まで落ちてしまった。 そのため、イギリス、ドイツ、フランスなどの欧州諸国が進めたのが、積極的な移民受け入れである。とくにイギリスは、旧植民地中心の移民受け入れで人口減を防いできた。しかし、その反動から、国民投票による「ブレグジット」が成立し、EU離脱となってしまった。 ドイツは、生活保護を受ける移民の増加、 移民男性による犯罪の多発などに苦しむことになった。 ■移民受け入れもやがて限界が来る それでも人口減少を解決する方法として、移民導入がいちばんであることは間違いない。どうやっても、少子化が止まらないのだから、移民に来てもらい、経済レベルが落ちるのを防ぐほかない。 しかし、移民を受け入れるためには、国のあり方を変えなければならない。 カナダがそのいい例である。カナダと言えば、「多文化主義」(multiculturalism)の国として知られるが、この多文化主義によりカナダは移民によるモザイク社会、多言語社会ができあがってしまった。 いまや、バンクーバーやトロントに行けば、あらゆる人種に出会う。ニューヨーク以上の「人種の坩堝(るつぼ)」である。 多文化主義においては、移民はそれぞれの出生地の文化を尊重する権利を共有することになる。カナダは、多文化主義導入で成功した稀有な国である。カナダ経済は成長を続け、国自体も平和で繁栄を続けている。 移民が国家の繁栄をもたらすことは、アメリカにも言えることだ。20世紀が“アメリカの世紀”だったのは、移民政策のおかげだ。今後も移民の流入が続くなら、21世紀もまたアメリカの世紀となるのは間違いない。 しかし、トランプ前大統領の出現以来、アメリカの移民政策は曲がり角に来ている。不法移民の激増に、元からの住民の怒り、不満が爆発した。 つまり、元からの住民にとって、多文化主義、多言語モザイク社会は受け入れがたいのである。 そして、この移民導入政策には、最終的に大きな壁が待ち構えている。 それは、世界中の国が人口減に転じてしまえば、そもそもの移民がいなくなってしまうということだ。経済格差からの移民は続くかもしれないが、いずれ途上国は消滅し、人口増加から人口減に転じるのである。 こうなると、先進国は移民の奪い合いをすることになるが、はたしてそんな時代がやってくるのだろうか? ■少子高齢化先進国、日本の未来はどうなる? わが国は、世界に先駆けて高齢国家となり、少子化、人口減に見舞われている。いまや、1年で40〜50万人の日本人が消滅している。国立社会保障・人口問題研究所によれば、今後もこのペースで人口減が続けば、2100年の日本人は、現在の半分以下である人口5972万人にまで減ってしまう。 しかし、いまのところ、日本に人口減を止める手立てはない。日本人の国民性から見て、大量の移民を受け入れることはありえないし、この国の文化を多文化主義に変えてしまうなどの大冒険をするとも思えない。 人口減による経済衰退を「借金財政」によって下支えし、ずるずると衰退していく未来しか見えてこない。そのため、先見の明と能力があり、有為の人間から、この国を出ていくだろう。 トランプが去ったアメリカは、いままた、1人1人の国民が選択を迫られている。多文化主義、モザイク社会を受け入れ、来るものを拒まず、「開かれた国」を望むのか、それとも国境の壁を築き、「アメリカ・ファースト」と言って衰退する道を望むのか。 じつは、日本もそうした岐路に立っているのだが、それを自覚している国民はほとんどいない。 日本の歴史を紐解くと、過去に人口減少期は3度あった。最初は縄文時代の中後期。2回目は、平安時代後期から鎌倉時代にかけて。そして、3回目は江戸中期から後期にかけてである。そのいずれのときも、日本は内にこもり、経済は成長していない。 現状を見れば、この歴史が繰り返すのは間違いないだろう。 【読者のみなさまへ】本メルマガに対する問い合わせ、ご意見、ご要望は、以下の私のメールアドレスまでお寄せください。 → junpay0801@gmail.com ────────────────────────────────── 山田順の「週刊:未来地図」 ― 日本は、世界は、今後どうなっていくのでしょうか? 主に経済面から日々の出来事を最新情報を元に的確に分析し、未来を見据えます。 http://foomii.com/00065 有料メルマガの購読、課金に関するお問い合わせは、info@foomii.comまでお願いいたします。(その他のアドレスですと、お返事できない事がございます。御了承下さい) 配信中止、メールアドレスの変更はfoomiiのマイページから変更できます。 ログイン時に登録したID(メールアドレス)とパスワードが必要になります。 https://foomii.com/mypage/ ────────────────────────────────── ※このメールはご自身限りでご利用下さい。複製、転送等は禁止します。 ────────────────────────────────── ■著者:山田順(ジャーナリスト・作家) ■個人ウェブサイト:http://www.junpay.sakura.ne.jp/ ■Yahoo個人 山田順コラム:https://news.yahoo.co.jp/byline/yamadajun/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━