ウェブで読む(推奨):https://foomii.com/00049/2019121108395061590 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 渡邉哲也の今世界で何が起きているのか 2019/12/11 第2012回 チャイナスタグフレーション ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★チャイナバブル 企業物価指数が下落し、消費者物価指数が上昇 景気悪化の中で物価が上昇するスタグフレーションを示しています。また、企業のデフォルトも増加し、融資リスクが上がっています。高額消費の流れを示すといわれる自動車販売台数も17か月連続で前年割れとなっており、バブル崩壊が明確化してきました。 中国の場合、中国政府と国有銀行による官製融資、不動産の売却制限などにより、市場を無視したバブル形成とバブル崩壊の抑制が行われています。しかし、これも矛盾を抱えたものであるために逆に歪みが大きくなる構造なのです。例えば、不動産の売却を制限すれば売り物が出ないため、不動産価格の下落を抑制できますが、同時に買い手もいなくなるため、市場が正常に機能しなくなるわけです。そして、不動産ローンは消えてなくなるわけではなく、売却ができないためにローンが可処分所得を減らしてゆく、そうなれば国内消費全体が落ち込むことになり、それを生産する企業の業績を悪化させる。過剰生産により企業物価指数は落ち込み、企業の利益率を圧縮、企業の雇用や賃金を引き下げる。この負の連鎖が中国で起きているといえます。… … …(記事全文2,628文字)




































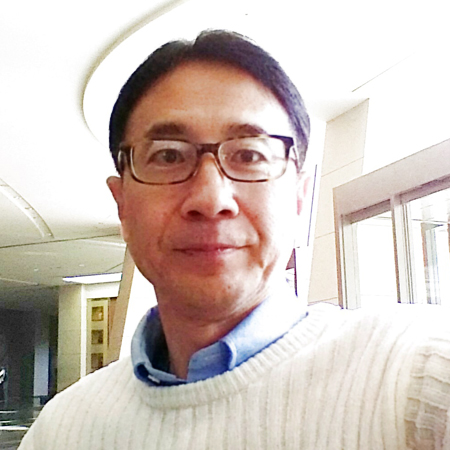






























購読するとすべてのコメントが読み放題!
購読申込はこちら
購読中の方は、こちらからログイン