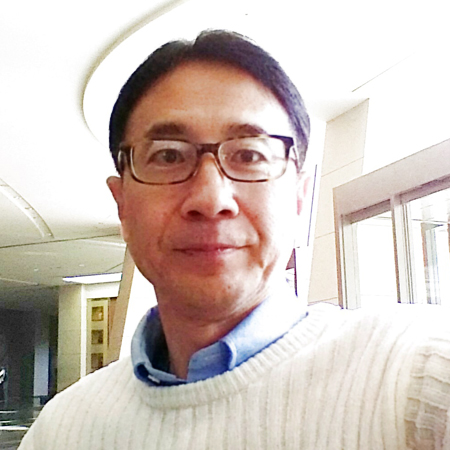■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ <1ヶ月にビジネス書5冊を超える知識価値をe-Mailで> ビジネス知識源プレミアム(660円/月:税込):Vol.1332 <Vol.1332号:増刊:金融危機の中核にあるデリバティブの意味(中編)> 2023年4月23日:632兆ドル(8京3000兆円)のデリバティブ契約とはなにか? 【テーマ(前編・中編・後編)】 アイマイな理解しかされてないデリバティブ(金融派生商品)を解説します。本質は「金融のリスク部分を証券化した金融商品」。2000年代の金融危機では、デリバティブでのカウンター・パーティの損失が中心になりますが、専門家の理解すら浅い。銀行と金融商品の危機から未然に逃げ自己資産の損を避けるにはデリバティブへの理解が必要でしょう。そのために書きます。 ウェブで読む:https://foomii.com/00023/20230423113004108252 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ホームページと無料版申し込み http://www.cool-knowledge.com 有料版の申込み/購読管理 https://foomii.com/mypage/ 著者へのメール yoshida@cool-knowledge.com 著者:Systems Research Ltd. Consultant吉田繁治 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 先週号で求めたご意見、ありがとうございます。100%が肯定的なものでした。1通だけ内容が難しい、具体と図解が欲しいというものがありました。メールマガジン内では図は描けないのでWEBサイトの参照にしています。著者にとって、役に立っていることは喜びです。野菜を作る農家が、美味しく食べる客を見て、やりがいを感じるように。 【個人の意見】 米国の大学では1時間くらい学説を教え「この人の見解は**を根拠に、この結論を導いている。君たちは、問題をどう考えるか?」と質問して、約30分の議論が始まる。授業は、発表の時間です。長女もおよそ毎日、日本では楽だった、こっちは大変だよと発表用のリポートを書いていました。 どこの国かの大学の「講義中は沈黙」とは違う。教科書が示す答えを出すことが、偏差値(中点を50とした標準偏差)で優秀とされる。考えるより漢文の素読の遺伝子にあるような、記憶のテストです。共同体の記憶を、個人が再記憶する。 自然科学以外の領域では、教科書そのものが、国のイデオロギーです。イデオロギーの典型である歴史の教科書は、国ごとに異なります。書かれた歴史は、多様な過去からある要素を取り出して強調し、価値観のある言葉で論理化したものです。歴史の教科書は、現代の価値観を示します。 国家は、自己の正当化のため「歴史」、現代までつながる物語を作ります。明治時代によく読まれた頼山陽の「日本外史(武家の盛衰記)」は江戸幕府の歴史観です。観は見方です。司馬遼太郎の歴史小説は自分のビジョンを投影したものです。「坂本龍馬」でも龍馬の歴史的な歩みをたどって、龍馬に託したビジョンを書いています。 日韓中は、第二次世界大戦では敵味方に分かれても物理的には、同じ経験をしたはずです。3国の歴史の評価は180度違います。天安門事件(1989年)も中国の現代史ではなかったことになっています。ウクライナ軍とロシア軍の発表が180度違うことと同じです。 日本の講座経済学は「翻訳の学問」です。このため「クルーグマンとバーナンキがこういっていた。ハーバードの大学院で**に就いて勉強した」と発言すると日本では優位になる。 森嶋通夫や宇沢弘文の説はノーベル賞級です。しかしなぜか引用しない。オーストラリア学派と金本位制も説くスティグリッツにもほとんど触れない。ケンブリッジで森嶋通夫に就いて学んだ人の経済学はクルーグマンとすいぶん違います。 日本の講座経済学は、通貨論では信用通貨制の優位を説く米国の新ケインズ主義に支配されています。何を仮説的な前提に置くかで異なっている経済学の学派のうち、新ケインズ主義を選んでいるのが日本です。選択の根拠はいわない。国際標準とだけ言う。この国では、「国際的」といえば、国内的より高い位置にある。 国「際」とは際、つまり境界の接触部分。日付変更線上あたりの飛行機の上か。あるいは、米国に向かう船上か、米国に上陸すればそこはもう国際ではない。米国です。それくらい曖昧な概念が国際です。 医学にも学派はあります。根本では診療の実証に基づくので、違いは少ない。なお軍医だった森鴎外は、軍隊の給食から多かった脚気を誤診し、多くの死者を生みました。当時のドイツ医学では誤診とはされなかった。現代からみれば誤診です。経済学にも、こうしたことが頻繁に起こっています。 官僚、御用学派、政治家では「国際標準」が決まり言葉です。 この「国際」とはどこの誰のことか、何の根拠で標準にしたのか問うと、この「標準」の基盤が崩れます。 政治家がいう国際社会は、アメリカとG7です。このため、日米安全保障条約がなくなったあとのことは、想定にない。これが国民の文化、資産、命を守る政府の義務である国防のテイタラクです。 武力を独占する国家は、国民に対して国防の義務を負います。 そのために、国民は保険料のような税を払う。天才的な秀吉の検地・刀狩り以来(1582年~)、政府は国防の義務を負います。企業、教団、ムラが自衛力を持つことは、近代法が禁じているからです。 米国では、原理的に州が国家なので州兵がいます。 国民には政府からの自衛のため銃での武装権もあります。州法もあります。売上税や所得税、相続税も州で、異なります。二重の政府が、EU(26カ国)のような連邦と州です。 東大からエール大学に行った計量経済学の浜田宏一(異次元緩和と財政拡張を推進:安倍内閣の内閣府官房参与)の教え子の1人が、日銀の新総裁に任命された植田和男です。元財務省の野口悠紀雄とは反対の説を述べます。当方とも、逆です。 統計学的な実証が求められる医学は、根本がこれほど離れてはいない。しかし経済学では、政府政策の実行結果が実証されない。 つまり、共通の根拠がない。日銀は、10年推進して戦争並みの550兆円の日銀信用を使った異次元緩和の、効果検証をしない。 肝心な日銀信用そのものも、明らかにされていない。 政治家の権力の根拠は当選ですが日銀にはそれもない。 便宜上の資本(12兆円)があるだけです(現在は債務超過です)。 医学の領域では、厚労省では新型コロナCovid19に対するファイザー、モデルナのワクチンの効果は示しても、遺伝子組み換えと同じ人工のスパイク蛋白が作る後遺症の研究は、何かの目的で封印されています。ワクチン担当相だった河野太郎は、米国民主党、民主党時代のファウチとWHOの曲に合わせ、踊っているだけです。 ところが直近のニューズウィーク(NYタイムズ、ワシントン・ポスト紙と同じ米国民主党の過激派)が、「Covid19」は人工のウイルスであった可能性が高いという説を紹介するように変節しました。 原因は、2022年の中間選挙で、下院で共和党が多数派になり、調査委員会では陰謀的だった「Covid19の起源」の追求がされているからです。狡猾なメフィストフェレス風のファウチが関与した人工説が有力になっています。 それとともに、厚労省が依拠しているWHO(世界保健機構)も、風邪の症状にとどまる若年者には、ワクチンの接種を推奨しないと言い始めました。 米国民主党の時代は2023年に終わりました。バイデンはレームダックです。米国メディアの報道も、政治の空気をみて、徐々に転換しています。2024年には、すっかり変わるのか。 CNNの有線視聴者数は、ピーク(米大統領選挙の2020年)の5%しかない。有料の有線放送ですから、視聴数だけなら潰れています。当方も、2020年までCNNの視聴者でした。多くがねつ造や世論誘導の、ヒドい内容に、イヤ気はさしていましたが、登場人物を選ぶショー的にはおもしろかった。 米国では、放送や新聞が支持党派を名乗ることが許されています。立場の論では、同じ事件、経済、外交、戦争が逆にみえます。特定の立場からの「歴史」になるからです。法的正義の分断があります。 日本厚労省が、新型コロナの政策を変えるのは、いつになるでしょう。いつものように、米国から2年は遅れるでしょう。今、300人の医系技官は、議論の最中でしょうか。いや議論せず・・・おなじみの責任逃れの沈黙か。 日本では、日銀の政策も同じですが、「行政責任は、追及しない」。 第二次世界大戦でも、それでした。大蔵省以下の行政は、8月15日から一斉に文書を焼却して、証拠を消したのです。このため経済学も政治学も、育たない。 一般向けの発言が多い元財務官僚も,米国の一派に権威を借りる典型です。借りものの権威付けが、この国で通用していることを、情けなく思います。 医学のような実証のある経済学は行動経済学です。他は思想です。合理的に判断し、行動する人間という前提です。 行動経済学は、人の経済的な判断と選択には合理的ではない面があることを実証しました。ドストエフスキーも、デーモニッシュな人間を描きました。不利なこと、損なことを選ぶ。 行動経済学のエッセンスを示す、ダニエル・カーネマン、『ファストな感覚的判断、スローな合理的判断(ファスト&スロー)』はおもしろい。人間の選択の合理性という前提を崩せば、経済学の基礎が壊れます。 正統派とされる経済学では、1)複雑系と、2)行動経済学を認めない。このため経済分析や物価論、通貨論は、観念を描く小説家に似ているものになります。 つまり、「相手を説得する論争の一派」になっているのです。ソクラテスが、真実から乖離した「ソフィスト(修辞学派)」として嫌ったものです。古代から現代まで、都市環境と物質文明は変わっても人の思考方法は同じです。 MMT(現代貨幣論)は、実証のない制度的会計学(信用通貨のB/S論の主張)です。なぜ、こうなったのか、といつも思います。 MMTの立論の根拠は、信用通貨を法が通貨と決めるから、通貨であるというものです。法は倫理を元にしています。法は、本来は、民間の通貨を決めることはできない。その証拠に法に規定のない仮想通貨が通貨になったでしょう? 2025年、2026年からまだ、現在の通貨との関係がどういったものになるのか不明な仮想通貨(デジタル通貨)が発行される計画です(日銀の黒田元総裁の言葉)。 2025年の大阪万博では、来場者の予定2800万人が公式の通貨として使います。(注)2026年からという、日本のデジタル通貨(CBDC)については、別の論考が必要です。 【変節したクルーグマン(民主党派)】 1990年代の後期、ゼロ金利の銀行預金が滞留して動かない「流動性の罠」に陥っていた日本に、法律貨幣の信用通貨(フィアットマネー)の異次元緩和とインフレ目標を薦めたのが、クルーグマンでした。(ノーベル経済学賞:2008年)。これも、本メールマガジンで紹介し、コメントしました。 (『復活だぁっ』山形浩生訳2001年:初出は1998年) https://cruel.org/krugman/krugback.pdf 15年後、アベノミクスの理論的なバックがこれでした。内閣府官房参与の浜田宏一が、安倍元首相首相に紹介し、安倍元首相は、主政策として実行したのです。旗振い役が、元総務大臣の竹中平蔵でした。. 最近の日本雑誌『Voice』では、本家のクルーグマンは「異次元緩和」は日本に効かなかったと白旗を上げています。社会で、価値と使い方を決める通貨論の根本に誤りがあったからです。 ドルと円は、信用通貨としては同じですが、借り入れ(米国では多い)、デリバティブの証券化金融(米国では多く日本では少ない)、預金(米国では少ない)、使い方(米国ではクレジットカーでも借り入れが多い)、国際性(ドルは海外でもそのまま使える)は異なります。 FRBがドルを増発したときと日銀の異次元緩和では、通貨の、借り入れ、預金、使われかたが違ってきます。日本では預金に滞留するものが多い。米国では流通が早い。 「日米では血液(マネー)の性格が違うのに、大量の血圧増加剤を日銀が入れたのです」 「同じマネーでも円とドルの性格の違い」があるので、クルーグマンの計算とは違った結果が生じます。政府・日銀・浜田宏一も、これを無視していました。つまり、誤診です。しかし今も、日銀は間違っていたとは、認めない。 【通貨増加が経済成長をもたらさなかった】 信用通貨では、政府が総価値(=増刷金額×流通速度)を決めると考えていたのです。このため、信用通貨を増発すると価値が下がるのではなく、ケインズが淵源の貨幣数量説から経済を成長させるとしました。 ところが550兆円(GDPの100%)を増発しても、目標の2%インフレにはならず、GDPも成長させなかった。銀行の当座預金が5倍に増えるだけで、増えるはずの銀行の貸付金(信用創造)の増加は、2~3%でした。増加率は、異次元緩和前と変わらなかった。 (マネーストック(M2)の増加は、2021年のコロナのとき特例で6.4%、2022年3.3%に低下、23年3月2.6%:M2は企業と世帯の 流動性預金です) https://www.boj.or.jp/statistics/money/ms/ms2303.pdf 異次元緩和は、所得が1/2になり、商品の購入が減っていく高齢化人口が30%に増えた日本では、ゼロ金利でも借り入れ増加による需要と投資の増加にならなかった(実証結果)。 5年前の2018年に、主唱者だったクルーグマンは、白旗を揚げてこれを認めました。政府・日銀は未だに誤診を認めず、植田日銀も金融緩和を続けるとしています。 【GDPは整備投資の増加で,実質的に成長する】 GDPは、預金(国民の消費の節約=エコノミーの原義)が、銀行の仲介で、借入金での設備投資になって成長します。それ以外での生産力の成長はない。 生産の設備投資(理系)を増やさず、需要(文系)を増やすだけでは、あとにインフレになります。これが、現在の世界的なインフレです。 (注)奇妙な形容で、単語につけた理系は数理的、文系は感覚的+観念的を示します。 ・音楽は、物理的には空気の振動です。われわれの耳と脳の感覚では音の色、メロディー、思想と情景を表現します。最近オーディオのことを書いていません。手入れすることが無限で、毎週1段階は(自分の独善では)進歩させています。 1980年の第2次石油危機以来、40年ぶりの世界インフレの前のコロナ対策で、日米欧の中銀は、2年間で、10兆ドル(1300兆円)の、(FRBは5兆ドルの国債・MBSを買って)、異次元緩和を実行したからです。これが、今回のインフレの主因です。 まずコロナでの、サプライチェーン・ショックが起こったといわれた。実質GDPの生産は増えなかった。米欧では、賃金が5%/年で上がり、財政支出と相まって需要が増えました。 ウクライナ戦争で価格が上がっても、需要は減らない原油・天然ガスのエルギーと食糧(穀物)、化学肥料の供給が減りました。 (理系である)設備投資がなく、逆に、コロナで減産されて生産が増えず、潤沢なマネーで、必需品の需要が増えれば、(理系である)経済成長のない、(文系の)インフレになるに決まっています。それが、2023年現在です。 日本では、国民が認めている日銀の、信用創造力を使って550兆円増刷しても、(理系である)経済を成長させる設備投資は増えず、生産性も上がらず、GDPの1人当たり生産性の函数である世帯の所得は、増えなかった(10年間の量的緩和)。世帯の所得が増えないと消費は増えない。 記憶では2018年だったか、日本が、異次緩和を開始して5年後のIMFの会議で、「日本は高齢化が世界1の人口構造から、量的緩和(マネーの増発)をしても、物価を上げるくらいの需要は増えなかった」とクルーグマンは、今回のVOICEのインタビューとおなじことを述べていました。 youtubeにIMF会議があったので、主なところを翻訳し、メールマガジンでコメントしました。メディアの報道は皆無でした。 NYタイムズのコラムニストのクルーグマンは風見鶏です。 過去の言動を覆す。最初は2001年に日本に薦めた異次元緩和(550兆円の国債の日銀による買い→550兆円の増発→40%の円安」もそれでした。 要は「日本の経済体質と構造を見ない、間違った治療だった」と述べたのです。無責任な話です。 政策を実行しない学者は、説を変えればいい。しかし説にのってやってしまった日銀は、買った国債の売りと550兆円の滞留マネーの回収ができない。株価だけは、3倍の水準に上げています(日経平均2万8500円:23、04.21)。それ以外では、1)約40%の円安と、2)円安による輸入物価上昇(40%台↑)、3)物価に対する実質賃金の下落にみえる、3大副作用が大きかった。 【袋小路の日銀】 「間違っていた」と言って、引き締め(国債の売り)を日銀がやれば、金利が3%、4%、5%と高騰して、政府財政は破産します(長期金利で1.5%から危なくなります)。これがゼロ金利と550兆円の日銀の国債買いで残った結果です。後戻りができず、引き締めへの出口もない。 1945年3月に沖縄が制圧されたあと、本土決戦しかないところに追い詰められ、ヒロシマ・ナガサキの原爆を落とされて無条件降伏した陸軍の再末期に似ています。軍は「日本が優勢」という大本営発表を、降伏前日まで続けていたのです。 植田新総裁は、「短期マイナス金利と金融緩和を続ける」という選択肢しかもたない。 岸田首相は、官僚が重んじる順列から次期総裁の番だった雨宮氏に、目星をつけていました。雨宮氏は固辞したという。「火の粉はかぶりたくない。最後は石をもって追われるから」ということでしょう。敗戦後の首相と同じです。 財務省も、有力な候補を出さず逃げました。日銀総裁のポジションの権威と人気は、経済成長(=実質所得の増加)という目的を果たせず失敗した異次元緩和のため、地に堕ちています。 1945年の、敗戦のときの首相と同じです(名前すら忘れられた鈴木貫太郎:1945-46の短期首相)。東条の跡を継ぐ鈴木は、雨宮のように、「とんでもないと固辞した」と記録されています。 日銀は、0.5ポイントの利上げすらできない。すでに国債の下落で自己資本を失い債務超過になっているので、2年後には、たぶん国が資本を出す国有化しかない。 肝心なことほど、日銀内の議論は公開されない。広報役の総裁の、文章(セリフ)を読む記者会見の言葉の、裏を読んで推測するしかない。 経済学は、中国共産党のマルクス主義と同じように、資本主義の党派的なイデオロギーですから、「表現されたことより、表現されなかったこと、肯定したことより、否定したこと」に重要な問題が隠れています。 下世話な比喩ですが、植田新総裁の、記者会見での表情は、妻から浮気の結果を追求され言い逃れようともがく夫にみえるのです。結果の修をする途(みち)がない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <Vol.1331号:正刊:金融危機の中核にあるデリバティブの意味(前編)> 2023年4月19日:有料版のみ 【正刊の目次:前編】 ■1.デリバティブの本質を示す代表選手はオプション取引 ■2.未来リスクと等価のオプション料 ■3.CLO、CDSはどんな証券か ■4.権利の行使 ■5.含み損、含み益=簿外資産、簿外負債 ■6.金利スワップ(契約総額6.5京円)の意味 ■7.権利の行使 ■8.設定価格で売る権利の、プット・オプション ■9.金融商品のリスクの意味(=デリバティブの意味) ■10.ボリンジャーバンド、証券アナリスト、ヘッジファド・マネジャーの方法 ■11.商品発注の、安全在庫との共通性 ■12.VIX(ボラティリティ・インデックス)の性質 ■13.未来は確率でしか表せない:だからデリバティブが生まれた ■14.複雑系の未来は確率でしか表せない:だからデリバティブが生まれた <Vol.1332号:日曜増刊:金融危機の中核にあるデリバティブの意味(中編)> 2023年4月23日:有料版・無料版共通 【増刊:中編の目次】 ■15.デリバティブ下落は、満期日までは簿外の損 ■16.簿外の損は、時間経過とともに露呈する 〔増刊の中編は、ここまで〕 <Vol.1333号:正刊:金融危機の中核にあるデリバティブの意味(後編)> 2023年4月26日:有料版のみ 【正刊:後編の目次予定】 ■17.米欧の不動産証券の下落 ■18.カウンターパーティリスクの構造 ■19.民間銀行の信用恐慌と、政府の中央銀行 ■20.信用恐慌は、10年サイクルだった ■21.資本主義の信用恐慌の代わりに、政府通貨のソ連ではハイパー・インフレ ■22.1945年~49年の日本 ■23.価値がなくなる信用通貨:価値を維持する金 ■24.2023年末からの問題の、焦点 【後記】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■15.デリバティブ下落は、満期日までは簿外の損 金利上昇によって、世界のGDPの6倍、8.2京円の契約の、全部のデリバティブに現れる損は、満期日までは損益が確定しないので、簿外の損です。すべての金融資産に、銀行は二重にデリバティブをかけているといっていい。デリバティブは、マネーそのものではなく「マネーの予想変動リスクの、等価交換の契約」ですから、目にみえない。 米欧が中心ですが、 ・世界の総契約額、632兆ドル(8京2000兆円)、 ・時価価値(=損益)、16.5兆ドル(2145兆円)です。 (表の一番上の行の、OTC契約額:22年6月時点) https://stats.bis.org/statx/srs/table/d5.1?f=pdf 末尾のカラムの時価価値(2145兆円)は、世界のOTC(銀行の店頭)のデリバティブでの、かけた側と引き受けた側の損益の合計を示します。 1)総契約額は632兆ドル。 2)22年6月時点の時価価値16.5兆ドルは、銀行間で、満期日に受け渡す義務がある金額です。 受けとる権利をもつ側と、支払う義務を負う側の、 ・総契約が632兆ドル(8京2000兆円)であり、 ・その契約の損益の合計が16.5兆ドル(2145兆円)の時価価値です。金利が上がる途中の2022年6月のものです。 【金利上昇で増える、デリバティブの価値(=損益になります)】 金利は22年3月から上がり、世界の金利を誘導するドルの米国では、23年4月で、2021年の3倍の5.0%になっています。 ↓ ◎デリバティブの損益は、金利の上昇に正比例して増えます。 金利と、ボラティリティを上げて、オプション料を計算すれば、これがわかります。オプション料(=デリバティブ契約のリスク価値)は、金利とボラティリティに正比例して増えます。 【デリバティブでの損失の推計】 米欧の銀行間で16.5兆ドル(2145兆円)だったデリバティブの損益(22年6月)は、その後の3ポイントの金利の上昇(2.5倍)により、約2.5倍の「41.2兆ドル(5300兆円)」に膨らんでいるでしょう(23年4月時点推計)。 銀行とファンドの満期前のデリバティブ契約に、5300兆円の損または利益(簿外の損益)が含まれているということです。 生命保険会社に例えれば、2023年から、5300兆円の保険金の支払い義務が発生するということです。 ■16.簿外の損は、時間経過とともに露呈する この5300兆円の損益は、いまはまだ、大部分(90%か?)が、銀行とシャドーバンク(ファンド)の、B/Sの裏の、表には現れない簿外の資産、または負債です。(注)金利が下がらないと、この損益は減りません、 時間が経過すると、満期の到来が増えます(減ることはない)。 ↓ 簿外の損益5300兆円から、米欧を中心に、大手銀行とファンド(シャドーバンク)の3か月の決算に確定した損益として、表面化するものが増えていきます。2023年、2024年と続きます。 【毎月、440兆円の損失が露呈】 1年で、既存デリバティブ契約の損益が表面化するとすれば、「5300兆円÷12か月=440兆円」が、毎月の確定額です。 1か月分でも、大手銀行の危機を生むのに十分な金額です。 2023年から24年初頭まで、米国と欧州の金利が、大きく下がらないと、損益の露呈は、確実になります。 【中編の結論】 以上が意味するのは、銀行危機は確実に訪れることです。 23年3月の、5つの中小銀行の、危機のあと、「金融危機は終わった」として株価上がり、楽観的な気分が広がっています。 2008年のリーマン危機のときも、株価下落の長期傾向なかで、短期の、4回の戻り高値のダマシがありました。これと同じにみえます。たぶん2023年末か2024年春が底値(-40%)、その間、3回から4回のダマシの株価上昇があるのでしょう。 * 有料版・無料版に共通の中編はここまでとします。後編の正刊は、4月26日に有料版として送ります。 【正刊:本編の後編の目次予定は以下です】 ■17.米欧の不動産証券の下落 ■18.カウンターパーティリスクの構造 ■19.民間銀行の信用恐慌と、政府の中央銀行 ■20.信用恐慌は、10年サイクルだった ■21.資本主義の信用恐慌の代わりに、政府通貨のソ連ではハイパー・インフレ ■22.1945年~49年の日本 ■23.価値がなくなる信用通貨:価値を維持する金 ■24.2023年末からの問題の、焦点 【後記】 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【ビジネス知識源プレミアム・アンケート:感想は自由な内容で。 以下は、項目の目処です。】 1.内容は、興味がもてますか? 2.理解は進みましたか? 3.疑問点はありますか? 4.その他、感想、希望テーマ等 5.差し支えない範囲であなたの横顔情報 があると、今後のテーマと記述の際、より的確に書くための参考になります。 コピーして、メールに貼りつけ記入の上、気軽に送信して下さい。 感想やご意見は、励みと参考になり、うれしく読んでいます。 時間の関係で、返事や回答ができないときも全部を読みます。 時には繰り返し読みます。 【著者へのひとことメールおよび読者アンケートの送信先】 yoshida@cool-knowledge.com 【送信先アドレスの変更や解約は以下よりお願いします】 マイページ(ログイン) https://foomii.com/mypage/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~