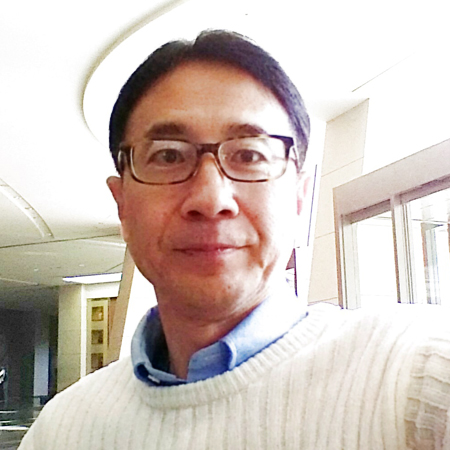… … …(記事全文2,060文字)言葉の定義は重要だ。
デフレーションは物価下落ではなく需要(=GDP)が萎む(デフレート)こと。インフレーションは物価上昇ではなく需要が膨らむ(インフレート)ことだ。
ということは、デフレ脱却とは「物価上昇」ではなく「需要拡大」を意味することになる。
もちろん、通常は需要が拡大すれば、物価は上昇する傾向が強い。ただし、需要拡大期に輸入物価が急激に下がる、あるいは消費税が廃止された場合、物価はインフレ期であるにも下落することになる。
だからと言って、デフレ突入とはならない。
デフレーション・インフレーションを「需要」と「供給能力」のバランスの問題であると理解すると、政府の国債発行や中央銀行の国債買取に対する見方が変わってくる。
需要とは、生産された財やサービスに対する支出である。財やサービスに対する支出とは、要するに「消費」と「投資」だ。消費と投資を合わせて「需要」と呼称する。
無論、日本国内ではなく、外国が日本国内生産の財やサービスを購入するケースもある。当然ながら、買い手が外国であったとしても、日本国内で生産された財やサービスに対して支出されれば「需要」となる。
需要の意味を理解すれば、デフレ対策とは、
「政府が国債を発行し、支出し、国内で生産される財やサービスに対して支出する(購入する)」
ことであると理解できるわけだ。
つまりは、中央銀行(日本の場合は日本銀行)の国債購入は、デフレ対策にならない。理由は、国債が財でもサービスでもないためだ。
日銀がどれだけ貨幣(日銀当座預金)を発行し、国債を購入しても、財やサービスは一円も買われていない。つまりは、インフレ(=需要拡大)効果は「ゼロ」だ。
例えば、国債100万円を所有するA氏と、銀行預金100万円を持つB氏がいたとする、。B氏が自らの銀行預金100万円を使い、A氏から国債を購入した。この時点で、インフレ(需要拡大・物価上昇)効果はいくらだろうか。
ゼロだ。
つまりは、日銀の貨幣発行・国債買取自体にインフレ効果はないのである。しかも、日本は2013年以降、日本銀行の量的緩和政策という社会実験により、それを証明してしまった。