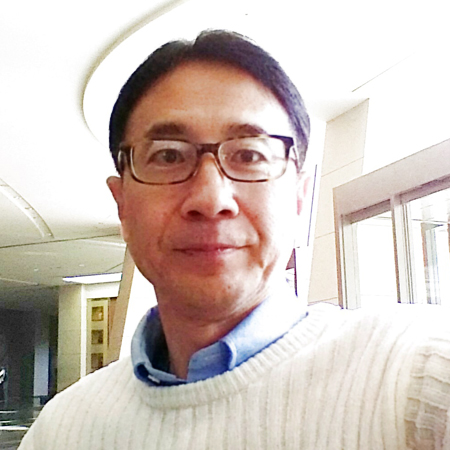… … …(記事全文2,232文字)意外と知られていないように思えるのだが、中央銀行の金融政策の基本は「金利」の誘導だ。
政策金利(無担保コール翌日物レート)の引き上げは、短期プライムレート(優良企業が一年以内の満期で借りる際の金利)を引き上げる。
政策金利の引き下げは、短期プライムレートを引き下げる
買いオペレーション(中央銀行の国債買取)は、長期金利を引き下げる。
売りオペレーションは長期金利を引き上げる。
ちなみに、短期プライムレートは住宅ローンの変動金利に、長期金利は固定金利に連動する。
中央銀行の金融政策とは、金利政策なのである。
上記を「伝統的」金融政策と総称する。それに対し、2013年に始まった「いわゆるリフレ派政策」は「非伝統的」だった。
「中央銀行がインフレ目標を設定し、インフレ目標を達成するまで量的緩和を継続するとコミットする」
ことで、期待インフレ率が上がり、実質金利が下がり、民間が借り入れを増やし、消費や投資という需要が増える。
という理屈のデフレ対策だったわけだが、結果はご存じの通り。結局のところ、紐で引っ張ることはできても、押すことはできない。
なぜ「いわゆるリフレ派政策」が採用されたのかといえば、当時の政策金利がゼロだったためだ。
金利がゼロであるにも関わらず、企業が借り入れを増やさない(需要が不足している以上、当然だが)。
となれば、期待インフレ率を高め、実質金利を下げる必要がある、という発想だったのだが、そもそもの問題は需要不足であった。
金利ゼロの状況で需要不足である以上、政府の財政政策で需要創出する必要がある。ところが、政府は緊縮財政。
緊縮財政を継続したとしても、デフレ脱却が果たせる「道」を、「いわゆるリフレ派政策」は示したのだ。財務省は、さぞや感謝したことだろう。
2025年1月24日、日本銀行は政策金利を0.5%に引き上げた。