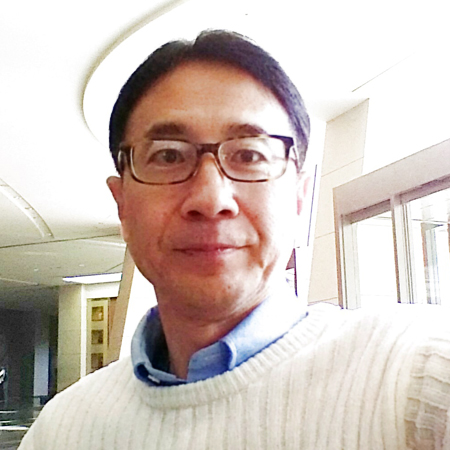ウェブで読む(推奨):https://foomii.com/00260/2022062015530795919 //////////////////////////////////////////////////////////////// 田村秀男ウェブマガジン 経済がわかれば世界がわかる https://gentosha-go.com/articles/-/43484?page=3&per_page=1 なぜ戦争は起きるのか。戦争を引き起こす原因はいろいろあります。第一次大戦後、昭和恐慌が発生し、日本経済は大混乱に陥りました。第二次大戦を引き起こす原因となる日本の大陸進出は、避けることはできなかったのでしょうか。日本経済の分岐点に幾度も立ち会った経済記者が著書『「経済成長」とは何か?日本人の給料が25年上がらない理由』(ワニブックスPLUS新書)で解説します。 https://foomii.com/00260 //////////////////////////////////////////////////////////////// 戦争の原因は経済というケースは多い ■大東亜戦争と経済 歴史的に戦争の原因が経済だったケースは多々あります。例えば日本が先の大戦を起こしたのも、やはり経済的に追いこまれたことが理由のひとつだったりします。 世界大恐慌があって、日本は満洲事変を起こして満洲国をつくりました。それはソ連の脅威に対処するのが大きな理由でもあります。中国に関していえば、その時点で結構な数の日本企業や居留民が行っていました。 その人たちが虐殺されたとか、テロに遭ったとか、いろいろなことが起きたわけです。そうなると当然、日本軍が日本人の生命と財産を守るためにという名目で出ていきます。それでドンパチが発生し、だんだんと戦火が広がっていった。 その後の盧溝橋事件で日中戦争に至りましたが、伏線としては日本が経済権益を得たい、つまり経済圏を中国大陸に広げたいという理由が大きかった。しかし、日本に石油をはじめとする資源の供給をしていたアメリカが日本を牽制するため、禁輸の措置をとりました。 日本は経済、そして軍を維持するために資源を求めてインドシナ半島に出ていかざるを得なくなった。それで南下作戦をとったということです。 インドシナ半島にまず行って、その次は当然のようにオランダ領インドネシアです。大きな油田がありますから。 ということで自ずとこれは米英を敵に回すしかないことになり、真珠湾攻撃という流れになった。日本が日米開戦を避けたいなら、最後通牒と評される「ハルノート」をのむしかありませんでした。しかし、もしのんだらどうなったか。満洲国は放棄し、インドシナ半島から撤退、中国大陸からも全面撤退です。 口では簡単に言えますが、そこに至るまで大きな犠牲を払っています。この段階で日本軍は相当な戦死者を出し、産業振興で結構な額のお金もつぎ込んでいますし、国民の精神は高揚している。ここでハルノートをのんで全面撤退なんてことになったら、東條内閣は退陣に追い込まれる。政治的にも経済的にも、そして軍事的にもどうにもならないという状況に追い込まれていったわけです。 こういう流れから見ると、先の大戦勃発の最大の原因のひとつは、中国における日本の経済権益の維持だといえるでしょう。それを確保するために、結局日本は開戦に踏み込まざるを得なかった。 日清戦争以降、日本は中国大陸に進出し、1932年、傀儡の満洲国を建てました。これは経済的にどういう意味合いがあったのか。まず満洲には鉄鉱石や石炭の鉱山がありました。だから、資源確保では進出の意味があるわけです。食料も、大豆や小麦の大規模生産ができました。満洲国を建国して、経済権益を確保するという動機は相当強かったはずです。 加えて日本国内は1929年の大恐慌の影響を受けた昭和恐慌の真っ盛りで、経済的にはひどい状態でした。第一次世界大戦が終わったあとの反動不況が昭和恐慌の発端のひとつです。 日本の大陸進出は避けられなかったのか どういうことかというと、第一次世界大戦中、戦場とならなかった日本の製品に対する需要は急増し、大戦景気に沸きました。しかし、戦後はヨーロッパの製品が市場に戻ってきました。日本は生産過剰になったため不況に陥りました。これが反動不況で、生産過剰を整理淘汰しなければならないという発想が強かった。整理淘汰のためには緊縮が必要だと。 一種のショック療法です。これを求める声がとくに財界から強かったわけです。あと、金本位制に復帰(=金解禁、金輸出解禁)したほうがいいという意見も強かった。第一次世界大戦のときには世界の主要国が金本位制から離脱していましたが、戦後次々に復帰し、景気が良くなっていたためです。日本もこれに乗ろうと、金本位制に復帰したのです。 金解禁は通貨価値を上げることを狙っていますので、緊縮財政、デフレ政策です。ただ当時は不況でしたから、そのときにデフレ政策をとるのはまったく辻褄が合わない手です。先に話しましたが、反動不況で生産過剰だから整理淘汰しないといけない、整理淘汰のためには、やっぱり緊縮が必要だという流れでした。 それで昭和恐慌が発生し、日本経済は大混乱に陥りました。海外に出ていくしかないという世論の強まりは、勿論ありました。国内で食い潰れて、可能性がない。ならば海外に出て行こうか。そういうときに満洲国が建てられ、多くの農民が集団移住し、満洲鉄道に代表される巨大インフラ整備もなされました。 それから財閥も鮎川義介の日産コンツェルンが満洲では大きな事業展開をしましたし、野口遵の日窒コンツェルン(いまのチッソ、旭化成、積水ハウスなど)は朝鮮半島に大規模な水力発電所をいくつも建てました。 明治維新以降、日本は拡大政策、富国強兵で成功してきたわけです。たまたま台湾と朝鮮半島では成功しましたから、拡大主義のイデオロギーが非常に強かった。繰り返しますが、満洲国建国は大義名分として防共、共産ソ連への対策もありました。 というのも中国では蔣介石が内戦ばかりやっていて、華北は軍閥の張作霖の天下で、彼に任せておいたら不安定なままなので、このままではソ連がやってくるだろうと踏んだわけです。すでに朝鮮半島は日本領で、鴨緑江を挟んだ向こうは満洲です。だから当時は防衛という理屈が当然のように発生しました。 一方の経済対策ですが、当時の列強といわれている国の基本的な考え方に帝国主義があり、満洲国建国で八方ふさがりの日本経済をなんとかしようとする意図はあったわけです。ある種の資本の運動というべきか、国内が望めないなら海外に収益機会を求めるのです。 当時国内マーケット、需要は第一次世界大戦後の不況とデフレで細っていましたから、海外に出て投資しようという資本主義特有の動機は本能的なものだといっていいでしょう。 当時はWTOやIMFといった、自由な投資の国際的枠組みがありませんでした。だから、早く行ったほうが勝ち、やったもん勝ちです。先に来ていた国を追い出す目的での戦争もあったでしょう。 あくまでも人間のやることですから、国民世論やメディアの論調など全体的な主張がものすごく影響しています。これらは政治に反映されますし、軍の行動にも結びついていくのです。戦前の大陸進出は、全体的な潮流を考慮すると、やはり避けられなかったのだろうと思わざるを得ません。 今後、日本はどう行動すべきなのか さて、今回のロシアによるウクライナ侵略戦争について、第1次、第2次世界大戦と比べてどうみるべきでしょうか。1,2次の大戦は唯一無二の覇権国の座をめぐるグローバルな争いという点で共通しています。第1次大戦は大英帝国に対する大陸欧州の軍事大国ドイツ帝国の挑戦で、米国が参戦することでドイツは野望が潰えました。第2次大戦はナチスによるドイツ第3帝国と、東アジアの大日本帝国がイタリアを加えた枢軸となり、米英同盟を中心とする連合国に敗れました。 米国は第一次大戦後、没落過程に入った大英帝国に代わる覇権国の座に座ることを避け、孤立主義をとる一方で、日本の封じ込めに努め、日本軍による真珠湾攻撃を誘発させ、参戦しました。そして欧州、太平洋でドイツ、日本を打ち負かし、唯一無二の覇権国としての座につきました。 覇権国米国の特徴は、軍事力だけではありません。基軸通貨ドルによる世界の金融市場とエネルギー・穀物市場の支配です。軍事力については旧ソ連の増長に直面し、冷戦時代に突入したわけですが、米国はドル覇権を駆使し、1次、2次の石油危機を経て、1980年代からソ連の収入の源泉であるエネルギー価格を低迷させ、ソ連崩壊へと導きました。軍事力ではなく金融力がソ連を打ち負かしたのです。旧ソ連崩壊を体験したのがKGB出身のウラジミール・プーチン・ロシア大統領です。 そのプーチンと2022年2月4日に盟約を交わしたのが中国の習近平共産党総書記・国家主席です。両首脳は「限りない相互協力」を北京冬季五輪開幕式時に約束しました。ウクライナ侵略はその20日後で、その間に詳細な協力項目が詰められました。その趣旨は、脱ドル依存のための金融協調と中国によるロシア産エネルギーと穀物の長期大量購入です。 両首脳は共に、帝国復興の野望を使命としています。プーチンはロマノフ王朝時代のロシア帝国、それを継承拡大させた旧ソ連帝国の復活、習近平は大清帝国までの版図を念頭に置いた「中華帝国の偉大な復興」です。それに立ちはだかるのが、米国のドル覇権です。ロシアにとってみれば、エネルギー、食糧ともドル建てで相場が決まり、米国の金融政策に翻弄される限り、ロシア帝国の再興は困難と考えるはずです。 中国のほうは世界の工場としてグローバル・サプライチェーンの元締めになったのですが、やはりドル金融に依存している限り、米国の圧力に屈せざるを得ない弱みがあります。習近平はグローバルな中華経済圏構想「一帯一路」を2014年に打ち出し、人民元経済圏への布石としていますが、中国経済そのものはドルの外貨準備がないと人民元金融・財政を運営できないのです。米国のドルによる世界経済支配力を弱め、グローバル世界での政治的影響力を拡大するうえで、プーチン・ロシアは格好のパートナーになったのです。 ウクライナ侵略戦争は戦況とは別に世界政治経済に重大な衝撃を与えています。エネルギーと穀物価格の急騰です。プーチンは2020年4月にサウジアラビアなど石油輸出機構(OPEC)を巻き込んだ協調減産を取り決めることに成功し、同年秋からの石油価格高騰を仕組んだ。新型コロナウイルス禍の世界の石油需要の低迷の機を捉えた。 米国の余剰ドル資金は石油投機に向かい、成功する。そしてウクライナ戦争の戦場と化した黒海での穀物輸送を困難にし、穀物価格を高騰させた。小麦の輸出市場のシェアはロシア21%、ウクライナ9%合わせて30%に上る。ヒマワリ油の国際供給の42%はウクライナ産です。欧州は天然ガス供給をロシアに頼っています。プーチンはもともと2014年以来脱ドルを着々と進め、ロシアに対して弱みを持つ欧州のユーロと、それを補完する形で人民元を取引通貨としてきたのです。 以上見ると、ウクライナ戦争はプーチンによるドル体制弱体化と、ドルを基軸とする米国の世界覇権の切り崩しであり、習近平が目立たない形で側面支援するという構図である。古典的なタイプの無法な帝国主義戦争とも言え、覇権国争いという点では第3次世界大戦の様相を限りなく帯びています。 野蛮で国際秩序無視の中露帝国主義に日本は直面しているのです。国際常識は通用しません。 日本はどうすべきか、中国をこれ以上増長させないよう、封じ込めと抑止の両面が求められる。生産、投資、金融、ハイテクすべての面で戦略を立てる。そのためには、日本の脱デフレ、経済再生、国力復興が前提となる。米国との同盟関係強化は当然だが、米国自体、台湾問題を含め対中強硬策はふらつき気味だ。日本はドル基軸を支える以上、米国への政治的発言力を強めるべきでしょう。 ロシアに関しては、中露同盟の分断を図るしかないが、具体的にはウクライナ戦争の今後の帰趨を待たなければならない。ただ一つ言えることは、ロシア経済の低迷は今後10年以上続き、ロシアが対中依存を強めるでしょう。それは中華帝国と国境紛争を繰り返してきたロシア帝国の歴史からすれば、プーチンのジレンマです。 他方で、侵略主義ロシアが日本に北方領土を返還するどころか、北海道への軍事侵攻すらやりかねない危険性をもはらんでいます。日米安保に安住し無思考の現状から覚醒すべきなのは言うまでもないですが、繰り返すように自らの国力再興と防衛力の抜本的な増強を同時並行して進めるべきです。 //////////////////////////////////////////////////////////////// 本ウェブマガジンに対するご意見、ご感想は、このメールアドレス宛に返信をお願いいたします。 //////////////////////////////////////////////////////////////// 配信記事は、マイページから閲覧、再送することができます。ご活用ください。 マイページ:https://foomii.com/mypage/ //////////////////////////////////////////////////////////////// 【ディスクレーマー】 本内容は法律上の著作物であり、各国の著作権法その他の法律によって保護されています。 本著作物を無断で使用すること(複写、複製、転載、再販売など)は法律上禁じられており、刑事上・民事上の責任を負うことになります。 本著作物の内容は、著作者自身によって、書籍、論文等に再利用される可能性があります。 本コンテンツの転載を発見した場合には、下記通報窓口までご連絡をお願いします。 お問い合わせ先:support@foomii.co.jp //////////////////////////////////////////////////////////////// ■ ウェブマガジンの購読や課金に関するお問い合わせはこちら support@foomii.co.jp ■ 配信停止はこちらから:https://foomii.com/mypage/ ////////////////////////////////////////////////////////////////