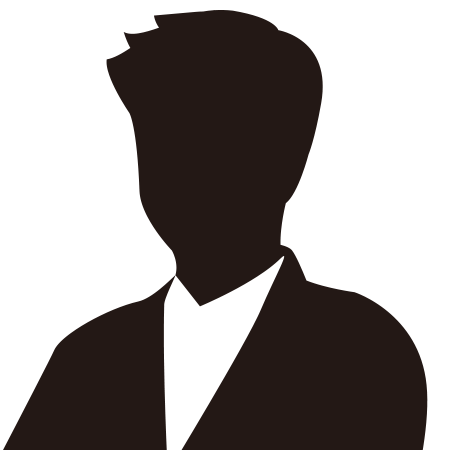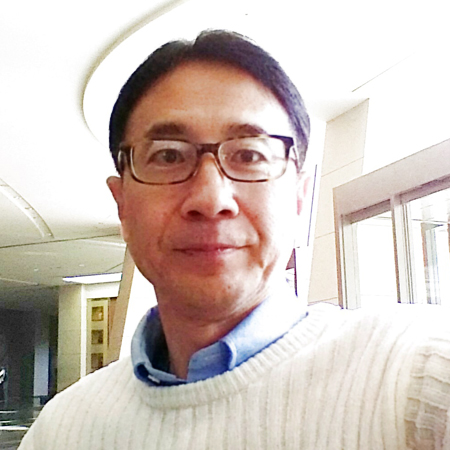□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 小菅努のコモディティ分析 ~商品アナリストが読み解く「資源時代」~ 2019年07月08日(月)発行 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ =================================== 6月雇用統計は良好な結果でも、予防的利下げの議論を停止させるのは困難か =================================== <良い数値だが、評価は割れた6月雇用統計> 金価格を決める要因は多岐にわたるが、2019年の最大の焦点が米国を筆頭とした世界の金融政策環境であることは間違いないだろう。2013年以降、米金融政策は専ら政策正常化を軸に調整が進められており、利上げと量的緩和縮小によって、市場から流動性を吸収する展開が続いていた。これは今年1~3月期、更には5月中旬頃までは変わらず、実際に今年4月30日~5月1日に開催された米連邦公開市場委員会(FOMC)では様子見スタンスを強調し、次の政策変更が利上げと利下げのどちらになるにしても、急いで政策調整を行う必要はないとの姿勢を強調していた。 しかし、5月上旬の米中通商協議が浮上に終わると、米国のみならず世界の景況感は急激に悪化し、現在はいつ米連邦準備制度理事会(FRB)が利下げに踏み切るのか、利下げに含みるとすればその回数は何回になるのかが焦点になっている。6月17~18日のFOMCで示された米金融当局者の「Economic projections of Federal Reserve Board members and Federal Reserve Bank presidents」をみると、2019年は9人が金利据置か利上げ、8人が利下げを想定していることが明らかになった。3月時点では利下げを想定している向きは存在しなかったが、今や利上げのカードはほぼ消滅し、利下げの有無に議論の焦点はシフトしている。… … …(記事全文3,857文字)