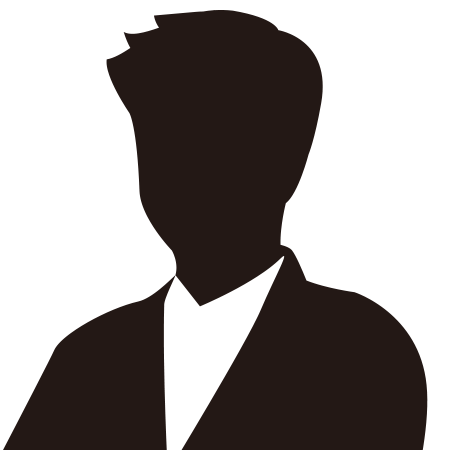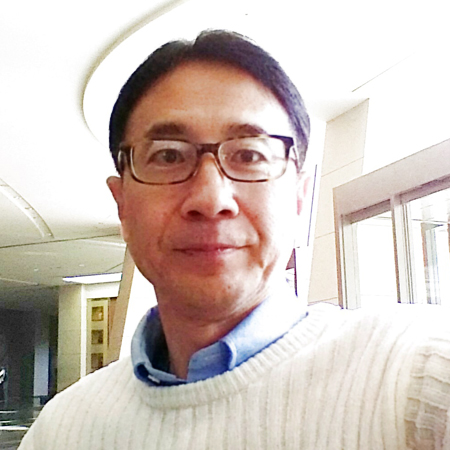□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 小菅努のコモディティ分析 ~商品アナリストが読み解く「資源時代」~ 2019年07月01日(月)発行 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ =================================== 大阪で決まったOPECの協調減産延期、OPECの危機感は強いが問題解決能力は? =================================== <OPECはトランプ大統領の増産要請を拒否> 7月1日に開催された第176回石油輸出国機構(OPEC)総会では、昨年12月に合意された協調減産体制の延長を決定した。現在、OPEC加盟国が日量80万バレル、非加盟国が40万バレル、合計120万バレルの協調減産が実施されているが、石油市場のファンダメンタルズの現状と見通しは、今後も協調減産の継続が必要と判断した訳だ。 昨年12月時点と比較すると、OPEC加盟国ではイランとベネズエラの原油供給環境が深刻な危機に晒されている。ともに米国の経済制裁の影響だが、1~5月期だけでベネズエラは日量43.1万バレル減の74.1万バレル、イランは同35.4万バレル減の237.0万バレルとなっており、78.5万バレルと決して小さくない規模の原油供給が失われている。だからこそ、トランプ米大統領は片方の手でベネズエラとイランに対する制裁圧力を強化し、もう一方の手でサウジアラビアを筆頭としたOPECに対して増産対応を要請していたが、OPECとしては減産体制の緩和・解消の形で実質増産を進めるトランプ大統領の要請には応えることはできないとの判断を下したことになる。… … …(記事全文3,859文字)