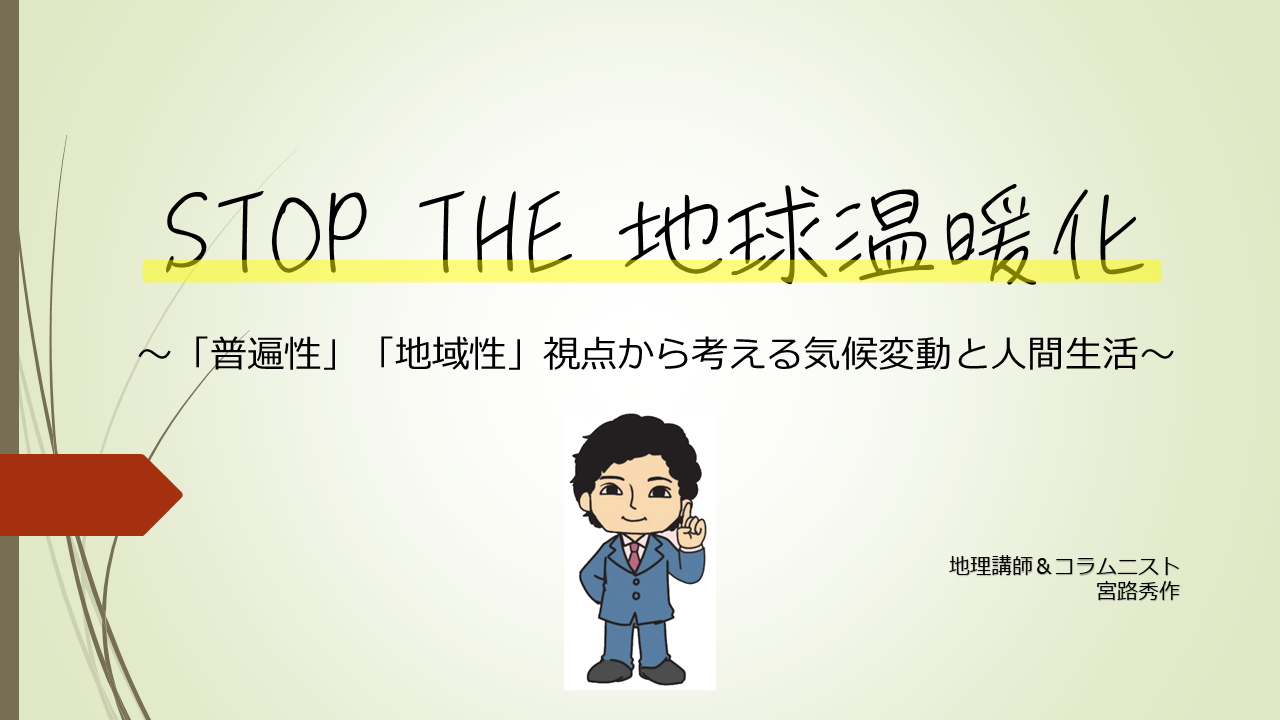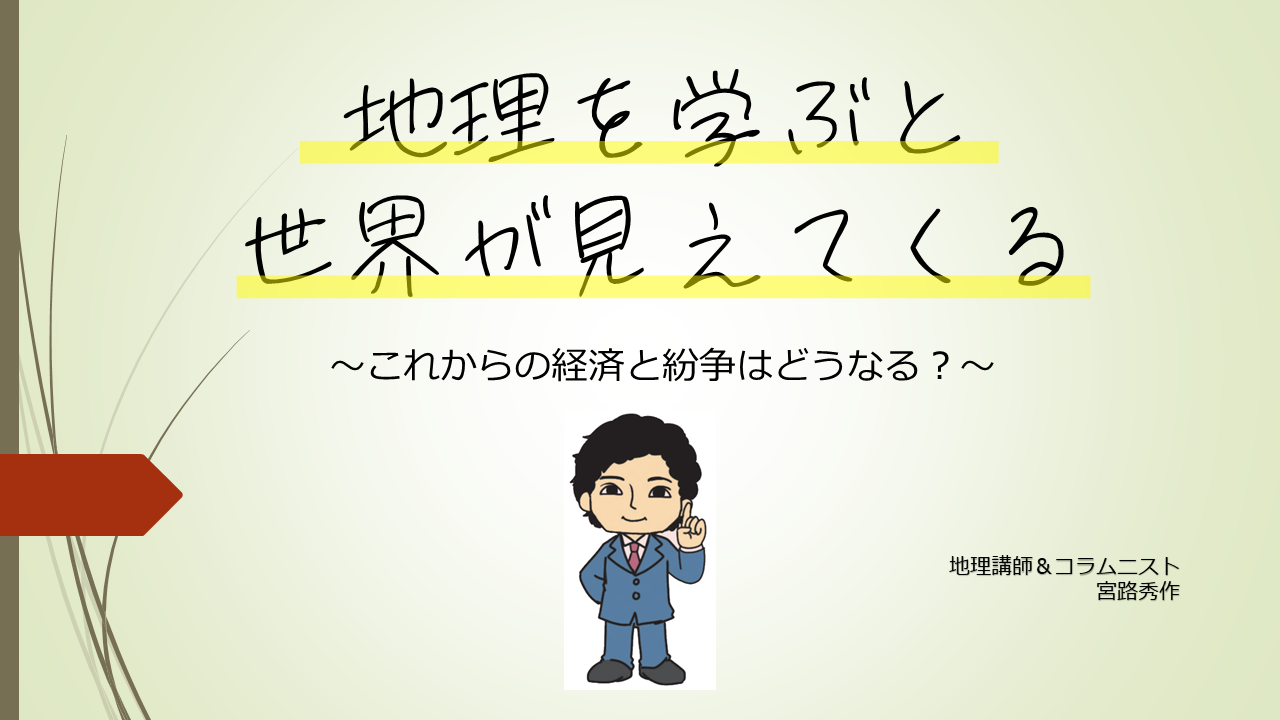… … …(記事全文6,817文字)
////////////////////////////////////////////////////////////////
やっぱり地理が好き
~現代世界を地理学的視点で探求するメルマガ~
////////////////////////////////////////////////////////////////
第128号(2023年10月26日発行)、今回のラインアップです。
①世界各国の地理情報
~中東情勢を早読み①~
////////////////////////////////////////////////////////////////
こんにちは。
地理講師&コラムニストの宮路秀作です。
日頃、周りの人たちからは「みやじまん」と呼ばれています。
今回で128回目のメルマガ配信となります。
10月となりました。
本メルマガのご購読を継続していただいたみなさま、大変感謝いたします。
ありがとうございます。
とはいえ、もう10月もあとわずか。
今号が10月最初のメルマガ配信となること、大変深くお詫び申し上げます。
これから、今号を含めて5本、今月中に配信する予定です。
今年は、講演会の機会を頂くことが多く、特に10月だけで2本の講演会に登壇しました。
一つは、茨城県の県北生涯学習センターが主催する、「STOP THE 地球温暖化~SDGs 何がおこる?何ができる?~」をテーマとした講演会でした。県北生涯学習センターは茨城県日立市にあって、自宅から車で片道およそ140km。往復280kmの道のりを、愛車のカローラスポーツで行って参りました。このガソリン代の高騰を受けて、泣きそうになります。
https://www.kenpoku.gakusyu.ibk.ed.jp/%E8%AC%9B%E5%BA%A7/page_20230324062405
▲講演のパワーポイントの表紙
もう一つは、一般財団法人中部生産性本部が主催する「2023年度人と企業の活力化フォーラム」。これの第2回に「世界の今と未来がわかる」をテーマにお話しました。
▲講演のパワーポイントの表紙
特にこちらの講演会では、「言葉の定義を明確にしておくことの重要性」を強調しました。「地理的思考力」「地政学」など、実に定義が曖昧な言葉を用いて、その状況を「ふわっ」と理解したつもりになっている人が多いように思います。しかし、実際には何となく理解している状態では真実には迫れないわけであって、挙げ句の果てには「察してよ」という、相手に丸投げする日本人の悪い癖が、世界で戦っていくには非常に足かせになります。
この講演会をきっかけとして当メルマガをご購読してくださった方がいらっしゃれば、大変嬉しく思います。末長らくご愛好いただければ嬉しいです。
「和を以て貴しとなす」は日本国内だけの概念であり、世界ではまったく通用しない概念です。こうした、国内と世界における自らの立ち振る舞いを使い分ける必要性が、ますます高まる時代になっています。それは得てして、「海外で良いとされているものを、無条件で日本に持ち込まない」ということなのであって、これを進めたことで苦しんでいる日本人が増えているように思います。
それにしても、講演会というのは緊張感があって良いですね。こういったお仕事を月に1~2本程度、ご依頼いただけるような人になりたいものです。「喋る」ことは、日頃から仕事としてこなしていますから、全然苦痛にはなりませんし、情報収集のあとに情報発信をすることで知識や理解が定着するものですから、こうした機会は積極的に得ていきたいと思います。
それでは、今週も知識をアップデートして参りましょう。
よろしくお願いします!
////////////////////////////////////////////////////////////////
①世界各国の地理情報
~中東情勢を早読み①~
以前、同志社大学の内藤正典先生のウェビナー形式による講演会を拝見したことがありました。内藤先生は、NHK高校講座「地理」にご出演なさっていた頃から存じ上げていて、「本当に頭の切れる方ってのは、こういうしゃべり方をするんだろうな」と憧れを抱いたものでした。そんな、わたくしにとっての「殿上人」みたいな内藤先生と、今となっては面識を頂く機会を得ることができました。今夏、同志社大学まで尋ねていったのですが、ゼミ室でマンツーマン、色々とお話を聞くことができました。大変感謝しております。
さて、上記の内藤先生の講演会のテーマは、「イスラームとヨーロッパ 共生はなぜ破綻したのか?」というものでした。
代ゼミの授業では、「共通テスト地理」「詳説地理講義」ともに、「宗教」の単元があります。もちろん、高等学校の地理にその単元があるからです。「宗教」を扱う場合、わたくしはいつも「無知こそ偏見を生む。『宗教』という言葉を聞くと、自ら敬遠してしまいがちだけど、偏見を持たないためにも正しい知識を持とう」と伝えています。
日本人はイスラームに対してどれほどの知識を持っているでしょうか。多くの日本人が「怖い」「怒ると爆弾持って走ってくる」といった、「イスラームによるテロ」ばかりに目を向けているのではないでしょうか。
そもそも、神や教会の権威から離れたことで個人の自由を得てきたのが西欧の価値観です。しかし、イスラームは神と共にあるからこそ自由が得られると考える価値観を有します。そう考えると、未来永劫理解しうることはないのだろうと先生は仰います。根本的に異なるパラダイムで出来た価値体系である以上、共生の接点は見いだせないのではないかと思います。つまり神や教会の権威から離れたことで自由を得たキリスト教徒と、神が定める範囲内で自由を享受しているムスリムとでは、「自由」ということば一つとっても分かり合えることはないということです。
昨今の日本でも、「多文化共生」を叫ぶ声が大きくなっているように思います。そして、それがあたかも「普遍的な価値観」であるかのように喧伝しますが、日本には日本の地域性というものがあるので、それを無視して「多文化共生」を導入しても上手く行かないどころか、多くの人を不幸にしてしまいます。
やはり、それぞれの地域に存在する地域性を無視する、つまり「互いに相手の歴史を知ろうとしてこなかったことが問題ではないか?」とも先生は仰っていました。日本人は、ビスマルクが残したとされる「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」という言葉をやたらと好む傾向にあります。しかし、多くの日本人は大河ドラマが好きであるように、歴史学を学ぶ重要性を感じているというよりは、単に「歴史のエピソード」が好きなだけのように見えます。
だからこそ、ヘーゲルは「『人間は歴史からは何も学ばない』ということを、歴史から学ぶことができる」といっており、個人的にはこちらの方が的を射ているように思います。歴史学を学ぶ意義とは、過去の出来事から教訓を学び、未来に活かすことです。しかし、多くの日本人は歴史学を学ぶことに時間を割く余裕がないのかもしれませんので、単に歴史のエピソードを楽しむに留まっているように思います。「秀吉が信長の草履を懐で温めた」というのは、歴史の「枝葉」なのであって、決して「幹」ではありません。こういう「枝葉」ばかりを集めても、実は歴史の真実には迫っていないわけです。