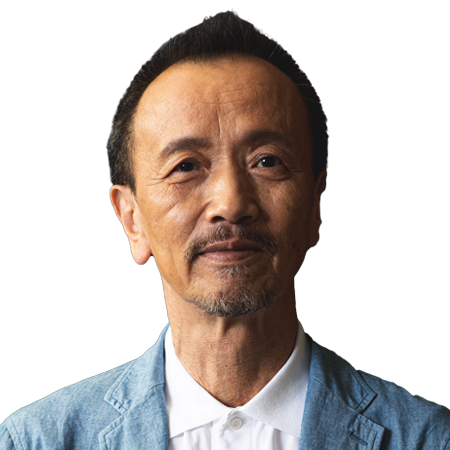… … …(記事全文4,997文字)●小学校は自宅と目と鼻の先
60年近く前、私が6年間通った小学校は、柏崎市立「日吉小学校」という名称で自宅とは目と鼻の先にある。校庭までの距離は100メートルもない。校庭の周囲には、市道に沿う形で立派な桜の木が植えられており、春の満開時には「桜通り」と呼ばれるほど花が咲き誇っていた。「桜の里」という名の広報誌もあった。
●トイレで男子児童が個室に入るのは「恥ずかしい」
学校に近いというのは何かと便利だった。朝ものんびりで、登校の準備に追われることもなかった。忘れ物をした場合も祖母から持ってきてもらい、校庭の柵越しに受け取っていた。もう一つトイレの問題があった。当時の男子児童は、学校のトイレで「小」は普通に使用しているのだが、「大」で個室に入ることは、「恥ずかしい」行為だった。誰かが我慢できずに個室に飛び込むと、目ざとく察知した者が「おーい、〇〇がうんこしているぞー」と言いふらす。そして、集まった児童が個室から出て来た児童を思い切り冷やかす。私も生理現象が抑え切れなくなったことがある。だが、冷やかされるのが嫌で自宅まで走って済ませた。私と同世代であれば、この不思議な習慣があったと思い出す方が多いのではないだろうか。この問題を除いて、平穏な小学校生活を送ることができたと思っている。
●少子化で強引に進む統廃合
今年の「日吉小学校」の卒業生は、20名で新入生は17名であった。私の時代は、それでも1学年で2クラスはあり、卒業生は約80名はいた。現在、住宅数は増えた。私が住んでいる町内も30世帯から130世帯に増加している。それでも児童数が少ないのは、やはり少子高齢化が進んでいることの証左である。この少子化対策として現市長は、合理化のみを追求し半ば強引とも言える手法で小中学校の統廃合を行っている。統廃合対象の保護者向けに説明会が開催されている。だが、市の方針を一方的に伝えるのみで、保護者の「複式学級でも十分満足している。却って中身の濃い教育が行われていると感じる」といった声は聞き入れられない。どこか原発再稼働の「地元説明会」に似ている。
「日吉小学校」から約10キロメートル離れたところにある「中通(なかどおり)小学校」は、来年度から「日吉小学校」と統廃合される。全児童数は約30名である。そこで、問題になるのが、学校名、校歌、校章などである。学校名は、対等の統合であるから、新しい名称ということで、「桜通り小学校」という安直な名称になる。私の時代の桜の木は、老朽化により伐採され、現在は細い桜の木に植え替えられているため「桜通り」と呼ぶには程遠い。校歌は、「日吉」という言葉が入っていないこと、由緒ある作詞・作曲家の作品であることから「日吉小学校」の校歌をそのまま使用する。校章は新しい意匠とする。こんなことを考えるのに時間を費やしている暇があるなら、今まで通っていた学校を離れ、スクールバスで新しい学校へ通う児童たちの気持ちを聞いてあげるべきではないか。
●卒業間近の期待と不安
私たちの卒業が近づいてくると、「中学校の上級生に怖い番長がいてチェーンを振り回しているらしい」とか「クラブ活動(部活)は何をしようか」といった話題が多くなる。進学する中学校は柏崎市立「西中通(にしなかどおり)中学校」である。柏崎市立「槙原小学校」の卒業生も同じ中学校へ進学して来る。
私は野球部に入りたかった。しかし、頭を丸刈りにするのが必須ということで躊躇った。野球と丸刈りにどういう関係があるのか理解することができなかった。その思いは今も変わらない。特に高校野球で丸刈りにしている姿を見ると違和感を抱く。戦時中を連想する。結局野球部へ入るのは止めた。他に興味がなかったので、消去法で卓球部へ入った。
●立ちはだかる恐ろしい人物
希望と不安を胸に入学した私たちの前には、それらを軽く吹き飛ばしてしまう恐ろしい人物が立ちはだかっていた。それはM校長である。赴任する先々で悪評を買った暴力校長であることを後で知ったのだが、それは酷いものであった。
●女子バレーボール部での暴力
M校長は女子バレーボール(9人制)が好きなようで、自ら指導していた。バレーボールコートの隣で卓球をしている私たちは、ある光景を見て凍り付いた。M校長がある生徒に罵声を浴びせたかと思うと、自分の前に呼び寄せて直立不動にさせ往復びんたを食らわせたのだった。さすがにグーパンチではなかったが、暴力を目撃したのはこの時が初めてだった。顧問の教諭もその場にいるのに黙って見ていた。今ならこれだけで一発アウト、懲戒免職は免れないだろう。だが、この「暴力指導」は日常的に行われていた。保護者(当時は父兄)は何も言わないのだろうか。退部させたら何をされるか分からないと怯えているのか。謎だった。そんな女子バレーボール部の試合成績は今一つ振るわなかった。いつ怒られるかと常に緊張状態で試合をしているのだから止むを得ないことなのだろう。