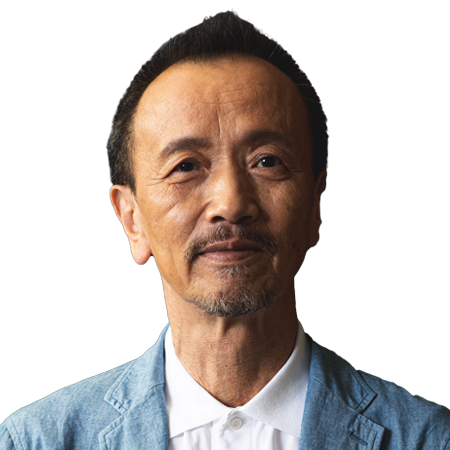ウェブで読む(推奨):https://foomii.com/00200/20230602053000109786 //////////////////////////////////////////////////////////////// 蓮池透の正論/曲論 https://foomii.com/00200 //////////////////////////////////////////////////////////////// ●束ね法「GX脱炭素電源法」の成立 束ね法「GX脱炭素電源法」が31日、参院本会議で可決・成立した。この束ね法は原子炉等規制法、電気事業法、原子力基本法など5本を一括して改定するものである。そして、福島第一原発事故から学んだ、原発の運転期間制限、新増設不可、原子力規制の独立性などのすべての教訓を真っ向から否定するものであり、狂気の沙汰としか言えない。 福島第一原発事故からわずか12年しか経過していない中での、政策の大転換である。基本に立ち返って考えてみたい。 ●「原発は安全である」という表現は誤りだった 私も現役時代「原発は安全です」と言い続けて来た。「放射能は、燃料ペレット、燃料被覆管、原子炉圧力容器、原子炉建屋という5つの壁に守られています」とか「多重防護の安全設計思想に基づき、設計・運転・管理が行われます」などと宣伝した。酷い場合は「安全なものは安全なのです」と全く論理性のないことまで語ったことがあった。だが、自責の念を込めて、遅まきながら正しく表現すべきだったと考えている。 原子炉の中では、自然界でほとんど起きることのない(天然原子炉は発見されているが)核分裂反応が臨界状態で継続している。大量の放射性物質が存在する。すなわち、原子炉内は危険で満ちているのだから、正確には「内包する危険を顕在化させないため様々な対策を取っています」と説明しなければならなかったのだ。 しかしながら、依然として電力会社の社員たちは絶対にそんなことは言わないだろう。一方で、原子力規制委員会は「基準に適合している」と判断はするものの「安全である」とは明言しない。原子力規制委員会の元委員長である田中俊一氏の「安全か、安全じゃないかという表現はしない」「絶対に安全だとは私は申し上げません」という発言は有名である。つまり、「自主的な努力により、安全性を追求するのが事業者の責務だ」と言いたいのである。 ただ、原子力規制委員会の判断が、一旦行政の手に掛かると「安全」に変わってしまう。安倍晋三政権時代の「原子力規制委員会が安全と判断した原発については、その判断を尊重し再稼働を進める」との方針に象徴されている。また安倍氏は「世界一厳しい基準」と豪語していた。 ●何が起きても不思議ではなくなった 2011年、福島第一原発で諸に「危険が顕在化」した。炉心溶融といった過酷事故の発生確率は、10のマイナス6乗、つまり原子炉1基当たり100万年に1回程度で「工学的には起こり得ない」のが通説だった。しかし、実際に起きてしまったのである。しかも、同時に3基の原子炉で、である。その発生頻度は(100万年に1回)×3、と天文学的数字になる。これが何を意味するかといえば、「何が起きても不思議ではない」、つまり「何でもあり」の世界まで到達してしまったということである。だとすれば、それまでの安全設計思想(原発とともに米国から輸入されたものだが)が果たして正しかったのか、原点に立ち返って再検討する必要があったのではないか。逆に言えば、新しく策定された基準は、あまりにも付け焼き刃的過ぎたのである。 ●安全設計思想とは 我が国のみならず世界中の原発で貫かれている安全設計思想は、国際原子力機関(IAEA)の「深層防護(Defence in Depth)」である。この「深層防護」(電力業界では軍事用語だとして「多重防護」と呼び替えることが多い)は、次の5つの層から成り立っている。福島第一原発事故後も、この思想の根本的見直しは行われず、新基準は踏襲する形で策定された。 第1層 異常の発生を防止する 第2層 異常発生時に、その拡大を防止する 第3層 異常拡大時に、その影響を緩和し過酷事故への発展を防止する 第4層 過酷事故に至っても、その影響を緩和する 第5層 放射性物質が大量に放出された場合、放射線影響を緩和する 大量の放射性物質を内包する原発では、一つの対策がうまくいかなかったときは次の対策で、それが破られたときには、さらに次の対策でと、第5層までの対策を設け、放射性物質を外部に出さない、あるいは影響を最小限に抑えるという基本的な考え方がとられている。… … …(記事全文4,535文字)