ウェブで読む:https://foomii.com/00263/20230313181824106652 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ASKA サイバニック研究所 ●比丘尼【びくに】は何? 2023年03月13日 ─────────────────────────────────── 比丘尼【びくに】は、「尼【あま】」の一字があることから、出家した寺の正規な「尼僧」とされ、「神仏習合(混交)」の時代から「巫女」に似た立場とされる。 中世(平安時代後期)の頃、天皇家の住持の尼寺を特に「比丘尼御所【びくにごしょ】」といい、天皇家、将軍家、摂関家に生まれた未婚の女性が、男性主体の寺と比べて戒律が厳しくない「比丘尼御所」で、比較的雅【みやび】な生活を送っていた。 天皇家の「三后【さんごう】」「三宮【さんぐう】」である、「太皇太后」「皇太后」「皇后」と、それに準ずる「准后【じゅごう】」「内親王など」の女性を「女院【にょいん】」と称し、「院」とは譲位を行った「太上天皇(上皇)」を指し、上皇の寵愛を受けた三后らは自ら「女院」として院庁を置いた。 特に未婚の内親王は、平安時代は「女院」となるが、時代が下ると「女院」は元のように天皇の后が成り、古代の「斎王【さいおう】」の制度が消えた結果、未婚の内親王が出家して「比丘尼御所」で生活を送ったとされる。… … …(記事全文7,999文字)


![コロナワクチン接種者は[脳溶解ゾンビ化]する!](https://m.media-amazon.com/images/I/51nD2d63m2L._SL160_.jpg)














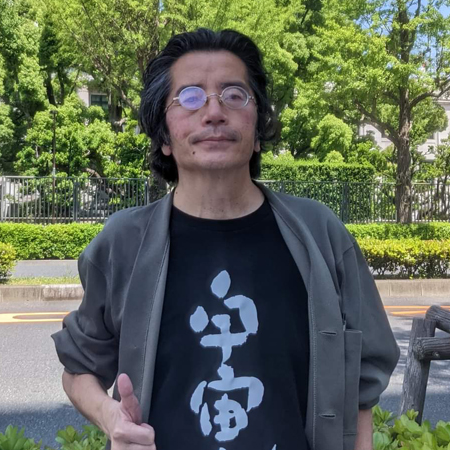








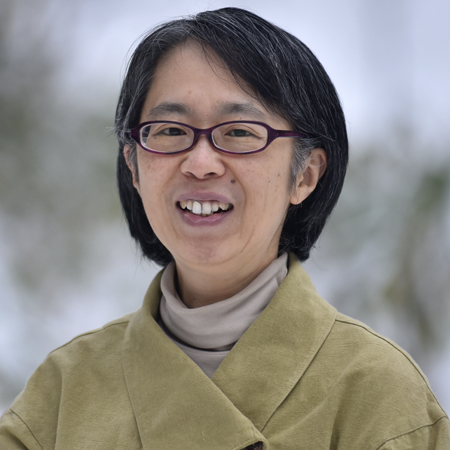






















購読するとすべてのコメントが読み放題!
購読申込はこちら
購読中の方は、こちらからログイン