ウェブで読む:https://foomii.com/00263/2022071222531696919 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ASKA サイバニック研究所 ●続・漢数字の謎? 2022年07月11日 ─────────────────────────────────── 漢数字には妙な仕掛けが他にも多数あり、たとえば「難しい」というのを昔は「六つかしい」と表記し、民俗学者の柳田邦夫、小説家の夏目漱石、歌人の伊藤左千夫も「六つかしい」と表記していた。 これは昔の和時計の時刻「六つ刻【こく】」から来ていて、朝の薄明の中を「明け六つ」、夕方の薄明が終わる「暮れ六つ」と表記、文字が見えにくい時間帯を表す意味から生じた慣用句と言える。 同様に「三時のオヤツ」は「お八つ」と書いたのは、「八つ刻」から来た言葉で、実際、江戸時代の「八つ刻」は今の午後2時~4時を指し、江戸時代は朝食と夕食の一日二食だった為、「八つ刻」に「小昼【こびる】」という間食をした。 江戸時代の「二八蕎麦【にはちそば】」も漢数字表記だが、うどん粉2&蕎麦粉8の合わせ比率説と、一杯2×8=16文説があるが、後者が正しいとする研究家が多い。… … …(記事全文11,963文字)


![コロナワクチン接種者は[脳溶解ゾンビ化]する!](https://m.media-amazon.com/images/I/51nD2d63m2L._SL160_.jpg)














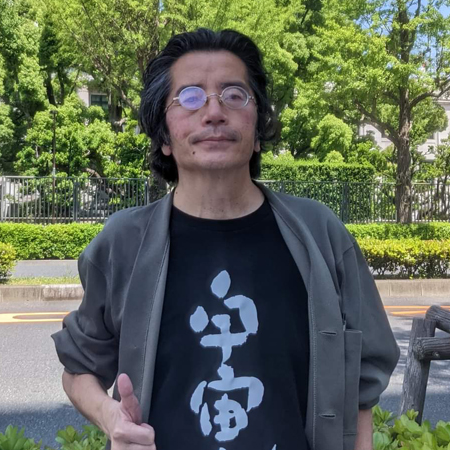








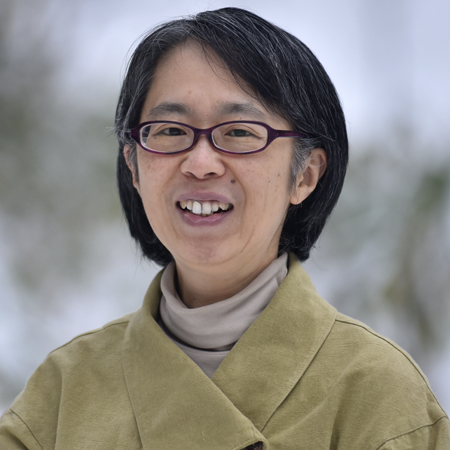






















購読するとすべてのコメントが読み放題!
購読申込はこちら
購読中の方は、こちらからログイン