… … …(記事全文3,109文字)「川田晴久読本: 地球の上に朝がくる 後編」(池内紀著・1980円・中央公論新社)
川田晴久の「あきれたぼういず」は当時、エンタテイメントのメインだった浪曲。このモノマネを三味線ではなくギターでやったことがウケたんですね。
あきれたぼういずが日劇に出たときには、お客が劇場のまわりを2回りしたほどです。
浅草に帰ってきたときは凱旋将軍そのもの。浅草松竹座は2000人も入る劇場です。それが朝昼晩といつも満員。お客はお金持ちではなく、丁稚、職人、職工など、貧乏な下層大衆ばっかり。不良学生とかね。それがエノケンの世界「与太者シリーズ」なんて、ミュージカルに熱狂してやんやと喝采を送っていたんです。
大正から昭和初期のモボ・モガ時代の空気ですね。モボモガなんて言葉はほとんど知らないと思います。モダンボーイ・モダンガールの略ですよ。日本人はなんでも短くするのが好きですからね。
浅草でモダンデビューを体験していた川田晴久は、4人組のあきれたぼういずを結成し、様々なジャンルの音楽を自在に取り込みました。浪曲にジャズやオペラなどをミックスしてパロディにしてしまう。自ら楽器を演奏して歌って演じてみせた。歌舞伎そのものです。
なんとも軽妙洒脱でモダンなセンス。なにより川田の歌声はいま聴いても天才そのもので、テノールで通るんです。


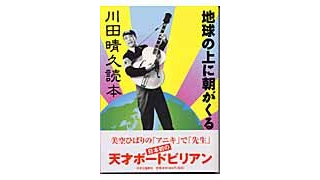










































購読するとすべてのコメントが読み放題!
購読申込はこちら
購読中の方は、こちらからログイン